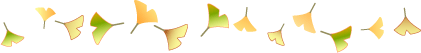
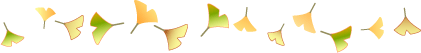
深 ま り ゆ く 秋
「人間と市民の権利の宣言」が憲法制定国民議会によって採択されたのは1789年8月26日のことだった。
全17条に及ぶこの宣言こそ、人類史上に残るフランス人権宣言である。
起草者はラファイエット将軍。
彼がかつて義勇軍として赴いたアメリカにおけるバージニア権利章典や独立宣言に基づき、絶対王政から立憲君主制移行への意図を有するものであった。
「おまえの誕生日に採択とは、偶然とはいえ、8月26日はわたしにとって一年でもっとも忘れがたい日ということになるな。」
オスカルは、人権宣言の全文に目を通したとき、満足そうにほほえんだ。
ようやく暑かった夏が終わり、妊娠後期に入ったオスカルは、目立ち始めた腹部を隠すため、常時夜着を着用している。
つわりの時期も過ぎ、切迫流産の気配も去って、さあ自由に動けると喜んだのもつかの間、腹部がみるみる膨張してきて、結局おとなしくせざるを得ない日々になった。
どこか自分の知らないところで、なにがしかの陰謀があって、そのために自分は絶対に動けないようにされているのではないかとすら思えてくる。
無論馬鹿げた被害妄想だ。
妊娠して腹部が大きくなるのは自然のことわりである。
誰がそんな器用な陰謀を企てるというのか。
だが、まじめな顔で追求されたアンドレは、オスカルをなだめるために、仕方なくパリの情報を収集することにした。
というのも、雑事に追われる日々から解放されて、アンドレに時間ができたからである。
二人だけではやはり何かと不自由だということで、夏の終わりに、アンドレはもともとこの屋敷を管理していた夫婦を、通いの雑用係として雇い入れた。
年老いてきて、農作業をするよりは給金をもらう暮らしの方がありがたい、と管理人夫妻は快く引き受けてくれた。
また、相前後して、バルトリ家に料理人も紹介してもらった。
舌の肥えたオスカルのため、侯爵が腕の良い男を見つけてくれたのだ。
こちらは、以前、庭師が住んでいた小屋に夫婦で移り住んできて、三度の食事の仕入れから調理までの一切を担当することになった。
この措置によって、アンドレの生活は格段にゆとりができたというわけである。
動けぬ不遇に、浮かない顔を続けるオスカルのため、アンドレはパリの情勢を教えてくれるよう、アランに手紙を書いた。
アランは、国民衛兵の幹部として、多忙の日々で、その居所も一定ではないので、直接届けることは難しい。
そこで、アンドレは、ジョゼフィーヌのもとに手紙を言付けた。
そこからクリスを経て、ディアンヌからアランへ、と手紙は渡った。
当然返事はアランから、ディアンヌ、そしてクリス、ジョゼフィーヌを経由してノルマンディーに届く。
このため、出してから返事が来るまでに、相当の日数を要した。
8月末に出された宣言をオスカルが手にしたのが、秋真っ盛りの今となったのもいたしかたないことだった。
しかも、当然ではあるが、仲介者の手紙もそれぞれに添えられていた。
さすがにディアンヌからのものはなかったが、クリスからは、禁止条項が箇条書きで添付され、ジョゼフィーヌからは、ベルサイユの現状とジャルジェ家の様子がしたためられていた。
が、どのような手紙でも、ないよりはマシである。
どんなに遅くとも、またどんなに耳に痛いものでも、誰かとつながっているというのは大切なことだとオスカルは思い知った。
ベルサイユ在住時には決して読まなかったであろうジョゼフィーヌの手紙もオスカルは丁寧に有り難く読んだ。
亡命を始めた貴族の名前が、バルトリ侯爵の話以上に増えていて、一方で、アラスに行くと言っていた将軍が出立を当面中止したとあった。
三人のベルサイユ在住の姉たちも、判断がつかず、苦悩している様子がうかがえた。
だが、最後はジョゼフィーヌらしく、妊婦は何も心配しなくていいから、とにかく無事の出産だけを考えるように、とくくられていた。
アランは、忙しいのだろう。
人権宣言の写しが一枚と、負傷したフランソワとジャンのその後だけが、簡単に書かれていた。
残念ながら、二人はケガの後遺症によって軍籍復帰は困難ということだった。
そこでジャンは養生を兼ねてラソンヌ家の雑用係、フランソワは、ベルナールの知り合いの靴屋のもとで修行を積むことになったとあった。
胸痛むことではあるが、フランソワもジャンも、もともとあまり体格が良い方ではなく、兵士になったのも生活のためだったわけであるから、こうして軍籍を離れるのは、むしろ賢明な判断だと言えた。
後見人として、アランとベルナールの名があれば、今のパリではさほど不自由なく住むところも仕事も得られるのだ。
弟に新しい靴を履かせてやりたいと言っていたフランソワの顔が浮かんだ。
「人生どうなるかわからんものだ。」
オスカルは、心底からそう言ってため息をついた。
自分が妊婦になっていることに比べれば、ジャンの雑用係やフランソワの靴屋のほうが、まだよほど自然だと思う。
素っ気ないアランの文面から、彼の充実した日々を読み取り、なんとなく置いてきぼりをくらったような切なさがわいてくるのをいかんともしがたい。
命を授かったことは、初めのうちこそ面食らったが、今は素直に嬉しいと思っている。
大切に育みたいとも思っている。
だが、不自由な期間があまりに長い。
こちらに移ってきた頃、庭に住み着いていた犬は、ちょっと腹部が大きいな、と気づいてからまもなく5匹の子犬の母になった。
なんとうらやましい、というのが実感である。
あの犬は、わずか2ヶ月ほどの妊娠期間を経て、5匹も生んだのだ。
なぜ、人間は10ヶ月もの長きにわたって懐胎していなければならないのだろう。
しかもたったひとりを生むために…。
「うらやましい…。」
ため息混じりのオスカルの声に、アンドレのほうがため息をつきたい思いだ。
「マリア・テレジアさまは16人のお子様をお持ちだが、その中もでプロイセンとの戦争を陣頭指揮されていたのだ。わたしにとってはもはや神業としか思えない。なぜわたしにはできないのだろう。」
犬をうらやましがるよりははるかにまともだが、稀代の女傑と比較して落ち込まれても、アンドレには返答のしようがない。
個性や個体差というものがあるのだろう。
それに、まさか女帝とて、馬に乗って戦場に出向かれたわけではあるまい。
だが、そのようなことを言ったところで、オスカルの気が晴れるわけではない。
激動のフランスの中で、ここだけが煮詰まってしまったような気配である。
アンドレもこうなってくると一日も早い無事の出産を祈るほかなかった。
といっても、出産後に身軽になったから、と馬を飛ばしてパリに向かうオスカルを想像すると、できるかぎりこの時間を引き延ばしたいという思いもあり、アンドレもまた、なかなか悩ましい日々を送っていた。
だが、この時、国王一家はベルサイユからパリに移されていた。
全く改善されない生活苦の中で、王妃が開いたはなやかな宴会が、パリの女性たちを爆発させたのだ。
オスカルの警護の下、何度も通ったパリへの道を、一家は涙と共に進んだ。
その知らせは、まだノルマンディーには届かない。
こちらでは、焦燥感の中にも穏やかな日々が、ゆったりと過ぎていた
![]() back
back![]() next
next ![]() bbs
bbs![]() menu
menu![]() top
top