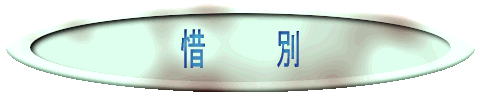フランス衛兵隊ベルサイユ駐屯部二階にある元司令官室の窓辺に、オスカルが日頃愛用していた椅子が、アンドレによって外へ向けて置かれた。
クリスの指示だった。
まだ窓は閉じられたままだ。
1789年7月10日午前10時、衛兵隊の全兵士が窓の下に集結していた。
きちんと整列はしているが、日頃に比べれば間隔が異常に狭く、男同士身体をくっつけるようにして立っている。
そしてその周囲を騎乗したダグー大佐はじめ将官が取り巻いている。
「おまえ、隠れて飲んだだろう?酒臭いぞ!」
「おまえこそ制服、たまには洗えよな。臭くてたまんねえじゃないか」
そこここで不満の声があがる。
だが、ダグー大佐の命令は、できるだけ広がらずに、司令官室の窓下へ集まれ、というものだったから、皆は互いの不平を我慢して、二階の窓が開くのを待った。
前任の隊長が退任挨拶をしたい、と現隊長に申し入れた。
体調不良のため表に出ることも馬に乗ることもかなわないから、馴染みのある司令官室の窓から閲兵したい、できれば全員に…、との要望を、アンドレを通して伝えられた大佐は、黙って近衛隊に使者を出し、衛兵隊の本日午前の警護を肩代わりしてくれるよう依頼した。
そして、事情を聞いた近衛連隊長ジェローデル少佐は、快く応じてくれた。
おかげで、こうして衛兵隊員は一人残らず、異例の退任式に参加可能となったのである。
すでにフランス全土から軍隊がパリに到着していた。
この配備には相当な無理が要ったはずである。
だが、二人はそういうことをおくびにも出さなかった。
アンドレは、表に現れない二人の配慮に心から感謝しながら、オスカルをそっと仮眠室の寝台から司令官室に運び、窓辺の椅子に座らせた。
すでに彼女は軍服に着替えている。
やややつれた感はあるが、久しぶりに兵士の前に出る、という緊張感が頬を紅潮させ、ピンと伸ばした背筋が、指揮官としての威厳を醸し出していた。
それは妻でも母でもない、一人の軍人の姿だった。
アンドレはゆっくりと窓を開け、自分はすぐに下からは見えないくらい後方に下がった。
隣では、クリスが、これまた緊張感を漂わせながら、鋭い目でオスカルを見守っていた。
窓が開く音に気づいた兵士からざわめきが起きた。
「隊長!」
一斉に声が上がった。
オスカルはにっこり笑うと、右手をあげ、兵士の動揺を制した。
「敬礼!」
職務に忠実な号令担当者が、条件反射的に声を発した。
隣の人間とぶつかりながら、兵士達は全員窓辺を見上げて敬礼した。
オスカルはゆっくりと答礼した。
「兵士諸君」
常より小さいオスカルの声が、皆を呼んだ。
その言葉を一言たりとも聞き逃すまいとして、兵士は一斉に口を閉じ、耳をすました。
「わたしは以前諸君にこう言ったことがある」
オスカルは語り始めた。
「心は自由なのだ…と。どんな人間でも、人間である限り誰の奴隷にも所有物にもならない心の自由を持っている…と…」
兵士の視線が一点に集中している。
誰もが、あのときのことを思い出していた。
ブイエ将軍の閲兵式をぶち壊し、営巣入りを命じられた兵士たちに、涙ながらに「心は自由だ」と訴えたオスカルの姿。
あの瞬間、自分たちは、隊長を隊長と認め、心を開いたのだった。
「今…あの言葉のあやまちを、わたしは訂正しようと思う。訂正というのが適当でないならつけくわえるといってもいい。自由であるべきは心のみにあらず。人間はその指先一本、髪の毛一本にいたるまで、すべて神のもとに平等であり、自由であるべきなのだ」
クリスの目が大きく見開かれた。
この人は何を言おうとしているのだろう。
彼女ははやる心臓に手をやりながら隣のアンドレを見た。
アンドレは、オスカルと同じように紅潮し、拳を握りしめ、真一文字に唇を結んでいた。
二人の心はいつだって一つなのだ。
クリスは再びオスカルに視線を戻した。
「わたしは除隊に伴い、女伯爵の称号とわたしに与えられた伯爵領のすべてを捨てよう」
「!!」
全軍に衝撃が走った。
さすがのダグー大佐もおののいている。
「わたしは、国王の、貴族の手先となって平民議員に銃を向けることはできなかった」
一呼吸おいて、オスカルは続けた。
「諸君もそうだった。わたしは諸君と同じ志を持てたことを誇りに思う」
「お、おれたちだって…!おれたちだってそうだ!!」
「われわれも誇りに思ってまいす!」
誰ともなく声があがった。
「そうだ!そうだ!」
一斉に賛同の声が広がる。
その様子を震える瞳で見渡すとオスカルはさらに続けた。
「今日を限りにわたしはここを去る。だが、心はいつも諸君とともにある。今後、どのようなことがあろうとも、諸君はおのおののの信念に基づき、自由に道を選んで行きたまえ!諸君の幸運を祈る!!」
「隊長!」
「隊長ばんざい!」
怒号のような万歳が繰り返された。
輝いた瞳に涙を滲ませ、兵士たちは持っている銃を天に向かって突き上げた。
オスカルはゆっくりアンドレに振り返った。
すっと歩み出たアンドレは、静かに片側の窓を閉めた。
「アンドレ!」
誰かが呼んだ。
アンドレの手が一瞬止まった。
「おまえも行くんだろう、隊長と…」
「あばよ!アンドレ!」
「達者でな」
「隊長を頼むぜ!」
アンドレは、熱い想いが心の底から沸き上がってくるのを感じた。
ひどい喧嘩や殴り合い、時に銃までぶっ放した奴ら…。
生身の人間同士の、隠しようもない生き様をぶつけあった奴ら…。
アンドレは閉じかけた窓から顔を出し、生涯最後の敬礼を、かけがえのない仲間に捧げた。
すると全員の敬礼が目に飛び込んできた。
彼はそれをしばらくながめ、そしてゆっくりともう片方の窓を閉めた。
熱い雫が一筋、頬を伝って落ちた。
クリスがすぐにオスカルに駆け寄った。
「大丈夫だ」
オスカルが言った。
「ええ、わかっておりますわ」
めずらしくクリスは逆らわなかった。
「お腹のお子様は随分と我慢強くていらっしゃいますもの」
クリスは泣き笑いの顔で言った。
「ご立派なご両親をお持ちなのですからね」
オスカルは、驚いてクリスを見返し、それからアンドレを見た。
アンドレも目を潤ませていた。
オスカルはクリスに向かってまっすぐ手を差し出した。
蒼い瞳に涙がにじみ、光を反射して、きらきらと輝いていた。
クリスは、そっとその手を取った。
オスカルが強く握りしめた。
クリスもまた強く握り返した。
最後の希望がかなった。
後ろ髪引かれる思いは、そう簡単に消えるものではないが、気持ちの切り替えは早いほうだ。
部下達はきっと、自分の思いをわかってくれたと信じよう。
オスカルはクリスに向かって言った。
「さあ、今からはおとなしい患者に戻る。指示を出してくれ」
クリスは、手にしたハンケチで涙を拭くと、にっこり微笑んだ。
「以前がおとなしい患者さまであったとは到底思えませんけれど、そのお心がけはご立派でございます」
ようやく本来の自分を取り戻したクリスは、力強く言った。
「では、お屋敷に帰りましょう。皆さまが首を長くしてお待ちでございます」