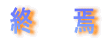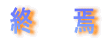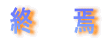
1792年4月20日、フランスはオーストリアに宣戦布告した。
革命を守るため。
革命をつぶすため。
まったく相反する両方の理由を、立場の相反するものたちから与えられた戦争であった。
「異国に嫁ぐというのは、こういうことなのだな。」
オスカルは天をあおぎ、マリーアントワネットの身上を思った。
そしてしばらくそのまま宙をにらみつけていた。
おそらく今までにもこういうことはあったのだ。
ヨーロッパの各国の王族は、きっと嫌になるほどこういう経験をしてきたのだ。
友好のために、あるいは領土のために、こちらの王女があちらの王子のもとに嫁ぐ。
あるいはあちらの王女をこちらの王子にめとる。
けれど、一旦同盟が壊れたが最後、嫁いだ王女は母国と戦うその先頭に立たねばならない。
「地獄だな。」
オスカルは視線をアンドレに移した。
その視線を優しく受け止めながら、アンドレは大胆なことを口にした。
「だが、不遜を承知で言うなら、今回の戦争でどちらが勝つことを王家は望んでおられるのだろうな。」
「当然フランスだ。と言いたいところだが…。」
オスカルは途中で口をつぐんだ。
「亡命した貴族が、革命を外から潰そうとして、諸外国にフランスへの干渉戦争を要求している。貴族が戦争を望むのは負けて革命を阻止するためだ。」
「そうだ。そして革命の同志たちは、そんな貴族を支援するオーストリアを許せない。亡命した貴族ごと葬ってやりたい。だから戦争する必要がある。断固革命を維持するために…。」
「負ければ革命が潰される。勝てば革命は存続する。」
「さて国王はどっちだ?」
オスカルはアンドレにわざと聞いてみる。
「考えるまでもないな。」
するりとかわされた。
国王が自国の敗戦を望んでいる。
自国民が戦禍を被り、他国に侵略されることを欲している。
あってはならないことだが、きっと真実だ。
遠いノルマンディーにいるからこそ、冷静に客観的に観察できる。
アントワネットが祖国に送る手紙には、フランス軍の弱点が列挙されていることだろう。
そしてそのことに民衆が気づけば、どのような惨事が展開されるか。
火を見るよりも明らかだった。
事実、事態はオスカルの予想通りに推移した。
怒り狂った民衆はテュイルリー宮殿に押し寄せ、、祖国の敗戦を願う国王一家を襲撃した。
国王は窮余の策として、議会に避難し、自身の身柄を革命議員に委ねた。
これにより、とりあえず国王の命は守られた。
だが王権は停止され、1792年8月13日、一家はタンプル塔に移された。
オスカルにとっては想定内の一連の出来事だったが、ルイ・ジョゼフにはそうではなかった。
彼の受けた衝撃は、かのヴァレンヌ逃亡事件によってマリー・テレーズ王女との交信が断絶されたときがかわいらしく思えるほど凄まじいものだった。
監視付きとはいえ、宮殿であったテュイルリーと違い、監獄として使用されているものだ。
しかも出入り口が狭く、要人の収監に最適な作りとなっていた。
もちろんもとから監獄として建てられたわけではない。
由緒あるテンプル騎士団の修道院だったのだ。
だが、それは今や昔のこと。
国王一家は、単なる政治犯とみなされ、裁判の準備が始まった。
そして、またもやルイ・ジョゼフの籠城が始まったのである。
ただ、今回は断食はしなかった。
そのあたりが前向きである。
前回のオスカルの教えを忠実に守っているのだろう。
危機に際してこそ、身につけた全てのものを活用すべし。
知識、教養、洞察力、それに計画力。
オスカルに丸抱えしてもらった前回と違い、できる限り自分の力で何とかしようとしている様子がうかがえた。
だが、籠城である以上、誰とも会わない。
もちろん、オスカルにも…。
したがって家庭教師は開店休業となってしまった。
オスカルが暇になった。
アンドレはそれが心配でならない。
なぜならば、暇なオスカルは碌な事を考えないからだ。
国家の情勢がこのようなときに、のんびり田舎に引っ込んでいられる性質では、断じてない。
フランスは戦争中なのだ。
しかも、戦況はきわめて厳しく、各地での敗北の知らせが届くところに持ってきて、地方からは王党派の蜂起が続いていた。
ひとりベルサイユに残るジャルジェ将軍はどうしているか。
危険が迫っているはずだった。
敗戦が続き、苛立つ民衆は、怒りの矛先を貴族に向け始めている。
自国の裏切り者を許すわけにはいかない。
民衆は王党派の貴族や司祭が幽閉されている牢獄を襲いだし、血祭りにあげていった。
恐ろしい光景だった。
そのようなところに父上をひとり置いておけるか。
オスカルは、家庭教師のためではなく、バルトリ侯爵と協議するため、侯爵邸に乗り込んだ。
アンドレは仕方なく同行した。
毎度のことである。
HOME BACK NEXT BBS