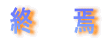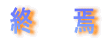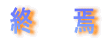
「スイス近衛兵の悲劇をどう思いますか?」
オスカルの厳しい視線から、一瞬目をそらそうかと思ってしまったバルトリ侯爵は、しかし実際には、真正面からそれを受け止めた。
「フランス人として、ただただ恥ずかしく、申し訳ない。」
その答にオスカルは少しホッとしたようだった。
オスカルが真剣に問うている時は、真剣に返す。
その大原則を、侯爵が、こういう質問に対してでも堅持してくれたことにアンドレは深く感謝した。
「きみは?」
侯爵がさらりと問い返した。
「わたし…?わたしは…。」
オスカルは黙り込んだ。
怒り狂っていたことを知るアンドレは、そのオスカルのとまどいを少し意外に感じた。
テュイルリー宮殿に民衆がなだれこんで来た時、警護にあたっていたのはスイス近衛兵900名だった。
彼らは忠実に任務を執行していた。
つまりは、押し寄せる民衆と国民衛兵を相手に懸命に戦っていたのだ。
しかし、この民衆の勢いに恐れをなしたルイ16世は、我が身を守るために敵の最高機関である議会に避難した。
意表をつく行動だが、冷静に考えれば、市民が襲ってこない唯一絶対の場所であったことは明らかだ。
国王は決して暗愚ではない。
そして国王は、自分を守ってもらうために、議会の意をくみ、先ほどまでスイス近衛兵に出していた防衛命令を発砲中止命令に変更したのである。
結果、王の命に従った近衛兵は、暴徒と化した民衆によって虐殺された。
とりあえず命だけは助かった国王一家は、この後、テュイルリー宮殿からタンプル塔に移された。
一報を受けたオスカルの怒りは激しく、あふれる涙をいくらぬぐってもぬぐいきれなかった。
命令を下すものは、下されるものの安全を何よりも重視しなければならない。
一隊を率いていたオスカルは常にそのことを肝に銘じていた。
自分の言葉ひとつで、人間の生死が決まるのだ。
なぜ、国王は発砲中止を命ずるに際し、民衆側にも武器を置かせるよう議会に交渉しなかったのか。
一方的に武器を置いてしまっては、坐して死を待つのと同じだ。
そんな命令を、どんな神経で発することができるのか。
さらには、いくら激していたとはいえ、近衛兵が発砲を停止した段階で、なぜ国民衛兵は攻撃を中断しなかったのか。
武器を持たぬものに、武器で攻撃するのは許されることではない。
かつて、ジェローデルは、民衆が武器を取る日まで待つと言った。
そして市民は武器を取った。
けれど、貴族が武器を捨てたのなら、市民も捨てるべきではないか。
その怒りを、しかしオスカルは、今、侯爵の前で理路整然と説明することができずにいた。
なぜなら、結局の所、オスカル自身も、激烈な怒りののちに痛感したのは、自国の混乱の中で、はからずも命を失う悲劇に見舞われたスイス人に対する罪の意識だったからだ。
この責任は一体誰が取るのだろう。
国王か。
国民か。
フランスという国全体が、大きな罪を負ってしまった。
しかも、そのことに、そういう罪を負ったことに、激流の中にいる人々は気づいてすらいない。
「侯爵とまったく同じ気持ちです。ただ申し訳ない。」
近衛兵のひとりひとりに、故国に家族がいたはずである。
その人々の涙を思う時、贖罪の念以外の何があるだろうか。
「父上はどうしておられたのだろう。陛下のおそばでなぜ諫言申し上げなかったのだろう。」
親国王派貴族の筆頭であるジャルジェ将軍は、除隊したとはいえ、それなりの発言権があったはずである。
まして、宮殿警護となれば、近衛兵の管轄だ。
スイス近衛兵に対しての配慮を進言すべきは、父をおいてない。
「それに、アランはどうしていたのだろう。なぜ国民衛兵に撤退、もしくは停戦を命ずることができなかったのだろう。」
国民衛兵隊において、実戦部隊の実質的指揮官になっているはずのアランは、このときどこにいたのか。
彼ほどの人物なら、武器を置いた敵に攻撃を続けることを決してしないはずである。
そして彼の命令なら全軍を動かすことができたはずである。
だが、結局の所、オスカルは傍観者でしかない。
混乱のただ中に身を置いてみれば、それぞれにもっともな言い分があるはずであり、安全な地帯に留まるものが、渦中にいる人間を口を極めて非難することは、最も恥ずべきことといえよう。
それを思えば、激高していたオスカルが、落ち着いた侯爵の贖罪の言葉の前で言葉数が減るのは無理ないことであった。
もはやこんなところに留まっていること自体が罪なのだ。
評論家になり果てた自分の姿に、唾棄したいほど嫌悪感を抱いている。
知らず知らず握りしめた拳が震えていた。
その様子を侯爵とアンドレは痛々しく見つめていた。
無口になったオスカルの姿が、言葉にならない全ての思いを物語っている。
自己嫌悪、罪悪感、後悔、無力感。
そこまで自分を責める必要は毛頭ないのに、一途に自分を追い詰めている。
彼女はそういう性格なのだ。
生まれてこのかた、そのように自分に厳しく生きてきたのだ。
こうなってしまった彼女が選択する道はただ一つ。
それを侯爵とアンドレは最も恐れていた。
温厚かつ沈着な二人からすれば、その道は暴挙であり、彼女以外の人間なら決して選ばないものである。
だが、彼女は選ぶだろう。
なぜなら、それがオスカル・フランソワだからだ。
その名前の続きがジャルジェであろうと、グランディエであろうと、そんなことはなんの縛りにもならない。
それを充分に理解しつつ、アンドレは思う。
彼女がその道を選んだら、フランスは変わるのか?
この混乱が収まるのか?
ありえない。
個人の力がそんなに大きいわけはない。
たとえ人より秀でた彼女でも…。
オスカル・フランソワでも、この混迷を見極め社会をまとめる力はないのである。
アンドレが顔を上げると、侯爵が深く哀しい瞳でオスカルを見ていた。
それからアンドレを振り返り、ゆっくりと首を左右に振った。
それは、オスカルの選ぼうとしている道に、否と言っているのか、それとも止めようとするアンドレに無理だと告げているのか、アンドレにははかりかねた。
たぶん、両方だったのかもしれない。
いや、侯爵自身、判然としていないのかもしれない。
ただ、侯爵は静かに首を振っていた。
HOME BACK NEXT BBS