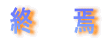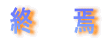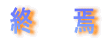
周囲の理解を得るという仕事をアンドレひとりに押しつけたツケは、すぐにオスカルに回ってきた。
前回のパリ行きは、全くもって良き前例などではなく、単なるオスカルの暴走だった。
そのように一族が認識していたことを、オスカルはようやく理解した。
オスカル、アンドレ、ルイ・ジョゼフの三人だったからこそ、アンドレの意見は少数否決されたが、一族会議では圧倒的にオスカルの主張の方が少数派で、同調してくれるのは結局、ルイ・ジョゼフだけだった。
だが、周囲がどれほど反対しようと翻意することはできない。
オスカルは断固、自身の意志を貫くため、ルイ・ジョゼフの計画がいかに優れているかを説き続けた。
そして不備を指摘されれば、進んで訂正し、また修正もした。
オスカルとしては相当妥協しているつもりだったが、計画実行には遅々としていたらなかった。
しかも反対勢力を勢いづけたのが、送り出すノルマンディー側だけではなく、迎え入れる側のパリ在住組もこぞって難色を示したことだった。
せっかく安全な場所で、家族揃って平穏に暮らしているのに、なぜわざわざ混乱のパリに出張ってくるのか。
シャトレ夫妻も、ラソンヌ家の人々も、アランも、誰一人快く受け入れると返事したものはなかった。
今やジャルジェ家は当主をのぞいて全員ベルサイユを離れている。
国外に去ったものすらいる。
それは何のためか?
ひとえに身の安全のためだ。
だいたい無位無職のオスカルたちがパリに来て何ができるというのか。
誰からもパリ受け入れを渋る手紙しか届かなかった。
中でも、もっとも強烈な言葉を送ってきたのはアランだった。
「はるかな西方にて国家を憂い、かりそめにも武官の精神を堅持されているならば、自分の役目というものを、もっと謙虚に設定すべきであると申し上げます。」
元部下の彼としては、最大限丁重な言葉を使いつつ、最高に厳しく戒めを書き寄越してきた。
「思い上がるなということか。フン!アランもえらくなったものだ。このわたしに説教してくれているぞ。」
オスカルは露骨に嫌な顔をして、その手紙をアンドレに投げつけたが、至極もっともな指摘であり、パリの現状の厳しさともども、もっときつく言ってもらってもいいくらいだとアンドレは人生で初めてアランに感謝した。
さらに周囲を過敏にさせたのは、ジャルジェ将軍から一切書簡が来なくなったことである。
短いものではあったが、こちらから出せば返事は必ず来ていたものが、冬に入ってぱったりと止まった。
ジャルジェ夫人の不安は極限まで増大していた。
こういう八方ふさがりの状態に陥った場合、昔のオスカルなら、四の五の言わせず、とっくにパリに行っているのだろうが、いかんせん双子がいる。
預かってもらうためには根気よく説得を繰り返すしかなかった。
親としての情愛は充分にあるゆえ、なすべきことを果たしたならばすぐにも帰ること、定期的に手紙を交わし互いの状況を確認しあうこと、等々、バルトリ家とジャルジェ夫人に約束した案件は箇条書きにした文書が束になるほどだった。
そのため、出発には長い時間がかかった。
本当に長い時間だった。
だが、将軍と連絡がつかないことが、かえって後押しした。
とりあえず様子を見てきてほしい。
夫人は最後にはオスカルに頭を下げた。
ようやくオスカルがアンドレ、ルイ・ジョゼフとともに出立できたのは、九月の王政廃止から四ヶ月近くたった一月半ば、計画を立て始めてからでも三ヶ月を経ており、すでに国王の裁判が開始されていた。
気がせくオスカルは、始めのうちこそ、旅程に余裕をもって宿もとっていたが、しまいには一昼夜走り続けて、疲れたところで小休止し、だがすぐまた出発という行程で、精も根も尽き果てる姿でパリにたどり着いた。
とりあえず目指すはラソンヌ邸だ。
ベルサイユのジャルジェ家はあえて避けた。
おそらく父も在宅しているかどうか確かではなかった。
反革命派への襲撃は断続的に行われていて、当然将軍にもその危険があった。
安全なところに身を移している可能性は高かった。
勝手知ったる路地に馬車を乗り入れると、異様な雰囲気が漂っていた。
興奮と静寂、感動と絶望、感激と衝撃。
相反するものが混在しているのだ。
もちろん戦争中なのだから、常時とは異なる緊張感がただよっているのは当然だ。
だが、それならば、むしろ一丸となった雰囲気があってもよさそうだ。
だが、それはなかった。
何かが対立していた。
ラソンヌ邸に入った三人は、そこで、その理由を知った。
前日の1792年1月21日、元国王ルイ16世の死刑が執行されたのだった。
HOME BACK NEXT BBS