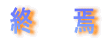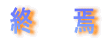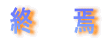
1754年8月23日、ルイ・オーギュスト誕生。
同年同月3日遅れて26日、アンドレ・グランディエ誕生。
1761年ルイが7歳のとき兄が、11歳のとき父が亡くなり、13歳になって母も死去した。
両親を失ったルイは祖父の後継となり、祖父の宮廷で王太子として育った。
1762年アンドレが8歳のとき両親が相次いで亡くなり、祖母に引き取られ、祖母の勤め先のジャルジェ家で従僕として育った。
生まれた日こそ3日しか違わないが、育った環境は天と地ほども違った。
アンドレにとって、ルイはまさに天上の人以外のなにものでもなかった。
関わりを持つことがあるなど想像だにしなかった。
だが、たまたまアンドレが従僕として仕えたジャルジェ家が、近衛の将軍家であったため、その後嗣もまた軍務につくことになり、従僕は護衛として宮廷に出入りし、そこでルイを見かけることになった。
もちろん、見かけるだけで、言葉を交わすことはない。
ルイはいつも大勢の取り巻きに囲まれていたし、彼自身が人と積極的に交わることを好んではいないようで、華やかな空間よりは、鉄さびで汚れた作業所にいる方が心安らぐ性格だったからだ。
一方のアンドレもまた、決して自分から前へ出る方ではなく、主人の陰に控えて、つねに主人のためによかれと動くことを生き甲斐とするようしつけられており、彼自身もそれをよしとしていた。
だから、少年時代の彼らはベルサイユというとてつもなく大きい同一空間にいて、決して交わることはなかった。
だが、ルイとアンドレが15歳のとき、異国から一人の皇女がやってきて、事態は一変した。
彼女はルイの妃となり、アンドレの主人の主人となった。
アンドレから見たとき、ルイは、主人の主人の夫になった。
ただし、普通なら、これで交わりができるはずはない。
だが、アンドレの主人が女性であったため、ルイの妃とアンドレの主人はごく親しい間柄となった。
有り体に言えば、アンドレの主人は王太子妃の寵臣となったのである。
そのため、ルイとアンドレは上座とはるか下座ではあるが、そしてルイは座していてアンドレは起立してではあるが、同じ室内にいる機会が生まれた。
無論、言葉を交わすことはない。
ルイは、大抵の場合、妃とは話すが、それ以外はにこにこと笑っている。
たまに、アンドレの主人に一言二言声をかけることはあっても、それだけだ。
さらにアンドレの主人もこびへつらってペラペラと話すタチではないので、下問に対してはできる限り短く返答し、あとは静かに護衛を務めるのみだったから、同一空間にいるとはいえ、ルイとアンドレの距離は、ずいぶんと遠いものだった。
そういう二人に、人知れぬ唯一の共通事項が生まれた。
これまた異国からやってきた一人の青年によってである。
この青年がやってきたのは、ルイとアンドレが19歳のときだった。
彼らより一つ年下の青年は、誰から見ても好男子でたちまち宮廷の話題を独占し、そしてあろうことか、ルイの妃とアンドレの主人の愛をも、独り占めにしたのである。
以後、ルイとアンドレはこの青年に対し、砂を噛むかのごときつらく苦しい思いを抱き続けることになった。
しかも、その思いは決して表に出すことができないもので、耐えるしかないのだという点でも共通していた。
ルイは、先祖に習って、いくらでも愛人をつくることができたが、決してしなかった。
アンドレは、独身の健康な青年として、自由に恋をすることができたはずだが、どうしてもできなかった。
ルイは妃だけを愛した。
アンドレも主人だけを愛した。
二人の悲劇は、相手の女性が自分たちを異性として意識するよりもずっと前に出会ってしまっていたことだった。
愛しい人と誰よりも近しく暮らしながら、二人は愛を得られなかった。
そして1793年1月21日、ルイは断頭台に消えた。
この世に生まれ落ち、父によってルイ・オーギュストと名付けられた彼は、やがてフランス王太子となり、父が反対していた妃を迎え、フランス国王となり、次いで市民によってフランス人の王となり、最後にルイ・オーギュストとして死んだ。
享年38歳。
国王刑死の衝撃から、オスカルもルイ・ジョゼフも一言も語らない。
その心中を察して、ラソンヌ家の人も誰も声をかけない。
二人は与えられた個室にこもったままだ。
だが、だからこそ、医師もクリスもロザリーもディアンヌやソワソン夫人でさえもが、アンドレに話しかけてくる。
ノルマンディーのこと、道中のこと、これからのこと、話題には欠くことがない。
その一つ一つに丁寧に応対しながら、アンドレは自分の心もひどく傷ついていることを感じていた。
ラソンヌ家の居間でにこやかに語り合いながら、胸が痛くて痛くて、涙がとめどなく流れそうで、普通に会話をしている自分が別人のようだった。
けれど、これで良かったのかもしれない。
こんな自分では、決してオスカルをなぐさめてやることはできない。
どんな言葉もかけてやれない。
それなら、ここでこうして皆の相手をしているほうが、ずっと救われる。
こういうときですら、こんなに傷ついていてすら、何か役目を果たしている方が気が紛れるのは、幼いときからの習性だろう。
厳しく育ててくれた祖母に今更ながら感謝した。
けれど思考はやはり国王刑死に戻っていく。
大好きな祖母の死は、深い悲しみをもたらしはしたが90歳の大往生だった。
人としてなすべきことはなしたとの安堵があったに違いない。
だが、ルイ16世は…。
そう思うと、またも心がちぎれそうになった。
だからアンドレは頃合いを見て、立ち上がり厨房に行った。
体を動かせば心がしばらくは放置されると思ったのだ。
そして床を掃除し、雑然とした道具類を片付け始めた。
医師とクリスとディアンヌは診察に戻り、ソワソン夫人は買い物に出た。
いつの間にかロザリーが来て、一緒に片付けをやってくれていた。
その大きな瞳が涙で潤んでいることに、しばらくしてアンドレは気づいた。
ああ、そうか。
ロザリーも泣けなかったんだ。
ラソンヌ家は貴族ではない。
王家と親しかった人など一人もいない。
むしろ、革命の旗手たちが集う場だ。
アランは革命の英雄だった。
ロザリーの夫は先頭で旗を振っているくらいだ。
だがロザリーは違う。
オスカルに連れられてベルサイユの舞踏会にも出入りした。
王妃に直々に言葉をかけられもした。
ほんの少しだけれど、遠くからではあるけれど、幸せだった頃の王家を知っている。
「相変わらず、俺たちは似たもの同士だな」
アンドレがポンとロザリーの肩をたたいた。
ロザリーの瞳からポロポロと涙がこぼれ落ちた。
アンドレは得難い同志を得て、ようやく自分の心を解き放った。
そして、亡き人の冥福を祈った。
そう、自分はまだ生きているのだ、と思いながら。
HOME BACK NEXT BBS