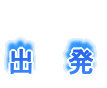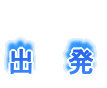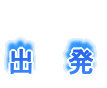絶対安静を理由に、食事はすべて自室で取っていたオスカルだったが、7月12日の夜は大広間で、両親、クロティルドとともに晩餐の席に着くことが許された。
無論パリにいるラソンヌやクリスとは連絡が取れなくなっているため、この判断は母である夫人によってなされた。
すでに出血が完全に止まって二週間がたち、吐き気もかなり収まって食欲が回復してきていることを考慮した結果だった。
こんなことなら、ラソンヌを屋敷に住まわせておくのだったと、将軍はこぼしたが、その申し出を受ける医師ではないことは、皆が知っていた。
まったく、肝心なときにおらんではなんのための侍医か、という将軍の恨み言は、いたってもっともであはあるが、長年、医師の希望を認めてきたのは他ならぬ将軍であったのだから、誰を責めることもできなかった。
クロティルドの船は明日出航とこちらの方は将軍が決定した。
ベルサイユ在住の長女、四女、五女にも、すでにその旨が連絡され、三人とも、明日は見送りに来るとのことだった。
久しぶりで出てきたクロティルドの滞在が一泊二日とはあまりに短いが、時勢が時勢である。
ジャルジェ将軍は友人のブイエ将軍の忠告もあり、一刻の猶予もならないと判断していた。
市民を扇動するような行為にまで及んでいた事実は、いかに動機が部下の釈放のためとはいえ、ジャルジェ家の人間に許されることではない。
嵐の前に、愛しい我が子を安全な巣の中にのがしたい。
このままここに置いておけば、きっとこの娘は軍をひきいて嵐の中に飛び込んで行くに違いない。
ひるむこともなくしりぞくこともなくまっすぐに戦いの矢玉の中へ向かって行くに違いない。
その前に…。
この夫の決意に、夫人は全面的に賛成した。
すでに親元を離れて長い次女に連れられて、生まれてこの方、片時も離れて暮らしたことのなかった六女が、明日、旅立っていく。
将軍も夫人も万感の思いが迫って、いつも以上に言葉少なに大広間に入ってきた。
オスカルとクロティルドは黙礼して両親を迎えた。
なぜ今夜、晩餐を許されたかは、すでにオスカルも承知している。
明日は船の上だ。
これは最後の晩餐なのだ。
着座し、ナプキンをとりながら、将軍は給仕をしているアンドレに声をかけた。
「明日はおまえも船に乗るのだろう。今夜は一緒にテーブルにつくがいい。」
思いがけない言葉だった。
主人と同席して、同じものを食するなど、おばあちゃんに知れたら、船に乗る前に殺される、とアンドレは震え上がった。
「い…いえ、だんなさま、今夜は…おばあちゃんの部屋で…。」
すると、夫人が笑った。
「ばあやにも同席するよう申しつけました。安心しておかけなさい。」
見れば、料理は六人分が用意されていた。
最後と知った上での、料理長の真心のこもった品々だ。
信じられないことだった。
アンドレは驚いてオスカルを見た。
だが、彼女はたった今までアンドレに視線を向けていたくせに、知らん顔で下を向いている。
立ち尽くすアンドレに、ラケルがオスカルの隣の椅子を引いてくれた。
本当に座っていいのだろうか。
本当におばあちゃんも同席するのだろうか。
ラケルにうながされ、おそるおそる腰掛けながら、動悸が一気に激しくなって、鼓動が隣のオスカルに聞こえているのではないかとすら思った。
ほどなく、オルガとブリジッドに両脇を抱えられ、ほとんど引きずられるようにしてマロンが姿を現した。
アンドレの予想通り、表情は完全に引きつっている。
長い使用人人生でも、ご主人様と同席しての会食など、おそらく初めてのことに違いない。
精一杯抵抗したのだろうが、オルガに、それでは自分たちが怒られる、と返されて、渋々ここまで来たのだろう。
「早く座れ。料理が冷める。」
同僚の百の懇願より、主人の一つの命令である。
将軍の言葉は絶対だった。
自分のせいで主人の食事を遅らせることなど、あってはならない。
マロンは急いでクロティルドの隣に座った。
夫人が優しくマロンにほほえみかけた。
食前の祈りが捧げられ、静かに、穏やかに晩餐が始まった。
「ねえ、ばあや。今日は粗相をしても怒らないでちょうだいね。」
クロティルドがコチコチに緊張して、何一つ手をつけずにいるマロンに話しかけた。
「そんな…!粗相だなんて。」
「あら、昔は随分厳しくしつけられたもの。こわい、こわい…!」
クスクス笑うクロティルドに、マロンの顔は真っ赤だ。
「長い田舎暮らしで、正式なお作法なんて忘れているでしょうし。ましてお隣が先生だとナイフを持つ手が震えるわ、ねえ、オスカル。」
クロティルドが、あえて使用人のばあやを先生と呼ぶ心遣いが、オスカルの心を優しく包んだ。
ばあやはまちがいなく、自分たち姉妹にとって人生の先生だった。
「おっしゃるとおり。昔、ガチャガチャと音を立ててはしかられました。」
「まあまあ、オスカルさままで、そんな…。年寄りをいじめないでくださいまし。」
そう言いつつ、食べたことのない豪華な品々とはいえ、貴族の屋敷に長年つとめ、子弟の養育をしてきた身である。
当然ながらマロンは食事の作法は知り尽くしていた。
「手が震えているのはあたしの方でございますよ。クロティルドさま。」
マロンはようやく自分を取り戻し、ナイフとフォークを手に取った。
「賑やかな食事もしばらくなくなります。ゆっくり味わいましょう」
夫人が皆を見渡した。
一瞬、時間がとまったかのように、皆の手が止まった。
こんな顔ぶれで食事をするのは、おそらくこれが最初で最後だ。
明日になれば、この中の半数であるオスカルとアンドレとクロティルドは船に乗って、ノルマンディーへと旅立つ。
また残りの半数である将軍夫妻と高齢のマロンは日を経ずしてアラスに向かう。
そして、ラケルやオルガたちは、こちらに残り、屋敷の管理にあたることが、すでにマリー・アンヌによって決められていた。
気がつくと、今日の給仕には使用人全員が当たっていた。
明日別れゆく人たちと、せめて最後の一夜を、そのひとときを、同じ場所で過ごしたい、という皆の思いが、自然にそうさせていた。
オスカルはそのひとりひとりの顔をゆっくりと見た。
ラケル、オルガ、料理長夫婦、門番一家、庭番夫婦、そして二人の厩係、三人の侍女。
心優しく暖かく自分を世話してくれた者たち。
屈託なく、自然に、立場の変わったアンドレを受け入れてくれた同僚。
そしてばあや…。
長く一緒にいたのに、ともに食事をとるのはこれが初めてだ。
作法は教わったが、一緒に食することは決してなかった。
誰より親しく近しいのに、隔てるものが存在した。
けれど、これからは、主と使用人ではなく、祖母と孫として、こういう機会を持ちたい。
けっしてこれが最後にはするまい。
それからゆっくりと両親に視線を向けた。
長年連れ添い、山を越え谷を越え、まったく別人格であるのに、まるで一つの絵画のように調和している。
いつか自分もアンドレとこのような雰囲気を醸し出せるようになるだろうか。
「受けた恩は親に返すのではなく、子に注ぎなさい。」
母からの心得は、実はもう一つ覚えていた。
それこそが最高の恩返しだと、母は言った。
深く深く胸に刻んだ。
「今生の別れでもないのに、なぜこんなに目頭が熱くなるのだろう。」
オスカルは小さな声でアンドレにつぶやいた。
アンドレは、そっとオスカルの手を握った。
BACK NEXT MENU TOP BBS