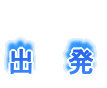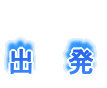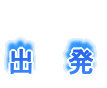名残のつきない晩餐も、やがて幕を閉じ、将軍と夫人が席を立った。
クロティルドも、部屋に引き上げた。
オスカルにはばあやが付き添った。
もう、そんな介添えは不要だと言いたかったが、明日からは望んでも得られないのだと思うと、黙ってされるままになった。
アンドレは晩餐の片付けにまわった。
同僚たちは置いておけ、と言ってくれたが、先に食べた自分が片付けるから、皆は厨房へ行って夕食を済ませろ、と請け合った。
アンドレがこの屋敷でする最後の仕事だ。
それを察して、皆はすんなりとアンドレの言葉に従ってくれた。
六人分の食器をアンドレは順番にワゴンで運んだ。
ありがたいひとときだった。
おそらく生涯忘れ得ない晩餐だった。
列席した面々に自覚があったかどうかはわからないが、アンドレにとっては義理とはいえ父と母と姉と、祖母と、そして妻と…。
家族と呼ぶのはおこがましいけれど、オスカルのお腹の子供から見れば、間違いなく、すべての人が血縁で結ばれている。
その輪の中に自分もいることが、怖いくらい幸福だった。
きっとおばあちゃんも同じ気持ちだったに違いない。
これ以上ないくらい目を細めていた。
涙は不吉、と奥さまに言われて、一生懸命こらえていたけれど、本当はどんなに泣きたかっただろう。
幸せと寂しさが入り交じって、何の涙かわからないまま、それでも泣きたかったに違いない。
厨房に食器を運ぶと、洗い物は自分たちがするから置いておけ、と料理長のギィが言った。妻のシヴィルも、オスカルさまがお待ちかねじゃないか、と笑った。
「というか、早くばあやさんから解放してさしあげないと、お気の毒よ。」
レイモンドが真顔で忠告してくれた。
そう言われて気づいた。
おばあちゃんがオスカルの部屋にいるんだ。
どれほど長い昔語りを聞かされていることだろう。
それはそれで、邪魔をしてはいけないような、けれども自分も祖母との時間をゆっくり取りたいような、複雑な思いがよぎり、結局アンドレは同僚の言葉に甘えた。
急ぎ足で階段を上がり始めたとき、バイオリンの音色が聞こえてきた。
静かで、少し物悲しくて、優しさに充ち満ちた、清らかな音…。
アンドレは踊り場でしばし足を止めその音に聞き入った。
オスカルの部屋の前まで来ると、曲は佳境に達し、音色は一層深みを帯びて、屋敷中を包んだ。
それを断ち切ることのないよう、できうる限り注意深く、静かに扉を開けた。
そして、窓辺で風に吹かれながら弦を奏でるオスカルの姿にしばし見惚れていた。
だが、音はすぐにやんでしまった。
アンドレに気づいたオスカルが楽器を離したのだ。
「おまえにモーツァルトは役不足だ。おまえの手にはもっとダイナミックな曲がふさわしい。」
一応、批評だけはしておく。
「フッフ…。なかなか耳が鋭い。」
オスカルにしては珍しく辛口批評に寛大だった。
「だが、これくらい静かな曲のほうが今夜にはふさわしい。選曲は間違っていないぞ。」
やはり負けず嫌いだ。
すんなりとは受け入れない。
「まったく同感だ。実はあまりに心に響いて怖いくらいだった。」
アンドレは正直に言った。
「ほう…!いつになく絶賛してくれるではないか。何か魂胆でもあるのか?」
冗談めかしているが、実はオスカルは照れているのだ。
こういう甘やかな曲を選んだ自分を一瞬で見抜くアンドレに対して…。
敏感で繊細になっているオスカルの心境を察して、アンドレはさりげなく話題を変えた。
「おばあちゃんは?」
そう、いるはずの人がいない。
「わたしを送り届けると、すぐに出て行った。」
「そうか…。」
物を言えば泣きたくなったのだろう。
誰よりも愛おしみ慈しみ育てたオスカルと、明日は別れねばならない。
祖母の胸中は察して余りある。
早々に退散したのも無理からぬことだった。
「出て行くときの最後の台詞がすごかった。」
オスカルがおかしそうに言った。
「え…?すごいって…?」
「産湯はきっとこのばあやがいたします。よろしいですね。ですから何があってもご無事でご出産まで持ちこたえてくださいまし…とさ。」
「…!!」
「すごいだろう。わたしは殺気すら感じたぞ。」
「アラスからノルマンディーまで来るって言うのか?」
「そうらしい。」
「あの歳で…!」
「執念だな。あの様子ではきっと這ってでも来るに違いない。」
「うーん…。まあそれだけ気合いが入っていれば、あと十年は生きてくれそうだ。」
「わたしもそう思った。だからつい言ってしまった。」
「なんて?」
「首を長くして待っているよ…と。」
アンドレには喜色満面で部屋を出る祖母の姿が見えるようだった。
さすがだ。
ツボを心得ている。
きっと蕩けそうな笑顔で言ってやったのだろう。
「そういうことがサラリと言えるから、おまえはあの恐ろしいヤキも蹴りも受けずに来られたんだろうな。」
ひがみのような台詞がつい口をついた。
オスカルが吹き出した。
「情けない声を出すな。」
励ましてやるつもりで、そっと背中に手を回した。
それから、そのまま顔を寄せた。
アンドレは動かない。
オスカルのやりたいようにさせてくれている。
暖かく広い背に、すべてを委ねる幸せを感じた。
「覚えているか。」
アンドレの胸に顔をうずめたまま、独り言のようにつぶやく。
「あの春のたまゆらに、おまえがいた。」
開け放した窓から、涼しい風が吹き込む。
「夏の日のめくるめく陽光の中におまえがいた。」
サラサラとカーテンが揺れる。
「いくたびかめぐった秋のたたずまいに、冬のそしりに…。」
サワサワと葉擦れの音が耳をくすぐる。
「さながらカストルとポルックスのように、おまえはいた。」
そのとおりだ。
その言葉をそのままおまえに返したい。
アンドレはゆっくりとオスカルの背に両腕を回した。
隙間なく寄せられた二人の鼓動が共鳴する。
「おまえは限りなく暖かい。ではわたしのわがままを聞いてくれ。わたしが臆病者にならぬよう、しっかりとそばについていてくれ。」
背中に添えられた優しい手とは裏腹の固い決意を秘めた言葉に、アンドレは、黙ってうなずいた。
そしてオスカルの方に向き直ると、しっかりと抱きしめた。
「地獄の果てまで、俺はおまえの影だ。」
唯々諾々とノルマンディーに行くようなオスカルではない。
ダテに春夏秋冬をともに過ごした訳ではないのだ。
アンドレはやりたいようにやらせつつ、何があってもオスカルと子供の命を守る決意をあらためて固めた。
7月12日の夜、懐かしい屋敷の懐かしい部屋で二人は最後の夜を過ごした。
BACK NEXT MENU TOP BBS