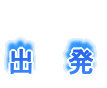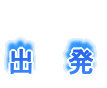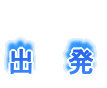運河に到達するまでの水路は小船がようやく行き違えるほどの川幅で、両岸には低木が等間隔に植えられている。
ベルサイユ宮殿の庭園内にある有名な巨大運河は、実は、本来池というべきもので、いわば閉じられた空間であるが、オスカルの船がこれから向かう運河は、その名の通りの運河であって、セーヌから引き込んだ水が、幾筋もの支流を抱えながらベルサイユをめぐって、ふたたびセーヌに戻っている。
小さい頃は格好の遊び場であったから、オスカルもアンドレもこの川筋については知り尽くしていた。
剣のけいこが早くに終われば、馬を引き出して遠乗りに行くか、舟のとも綱をといてこぎ出すかどちらかだった。
無論、そのような遊びから遠ざかってすでに20余年の歳月が経っている。
今、両岸に咲いている花が、あのときの花であるわけはない。
けれどもそこここの花や草木は、まるで年を取ることを忘れたかのように、同じ場所に同じものが変わることなく咲いていて、オスカルに不思議な感覚を与えていた。
きっと大人になっていく中で、自分たちが忘れ果てていた間も、繰り返し繰り返しこれらの植物は咲いては枯れ咲いては枯れ、季節を重ねてきたのだろう。
自分もこうなるはずだった、とオスカルは思った。
平和な時代であれば、そして男であれば、おそらく自分も、代々の当主が住む屋敷で一生を過ごしたはずである。
父祖が築いた地位と財産を継承し、それをそのまま子孫に伝えて、何事もなく家名も血筋も子孫に引き継いでいったに違いない。
そう、この両岸の花たちのように…。
だが、今、胎内の命とともに、自分は先祖伝来の屋敷を離れ、見たこともないはるかな地へ漕ぎ出そうとしている。
守護まいらせるべき王家にたてつき、その上に身ごもり、到底この地に住み続けることのかなわぬ身となった。
いつか再びこの地に戻ることがあるのだろうか。
あの懐かしい屋敷に、あの懐かしい部屋に、いつか戻れるのだろうか。
そして何よりも、父や母と再び会う日は来るのだろうか。
不安定な社会の有り様が、部下たちの出動という現実が、オスカルを珍しく悲観的にさせていた。
もとより速度の上げられるはずもない手漕ぎの舟だが、身重のオスカルを乗せているため、一段と緩やかに進んでいく。
まるでオスカルに決別の時間を与えてくれているように…。
「さら…ば。」
小さい吐息のような声でオスカルはつぶやいた。
「さらば、もろもろの古きくびきよ。わたしの部屋よ。父よ…母よ…。」
水門を出るときほとばしり出た涙が、再びわき上がってきた。
戻れないと決まったわけではないのに…。
二度と会えないと決まったわけではないのに…。
我ながら感傷的になっているな、と思ってフッと顔を上げると、向かいに座っているクロティルドが、大きな帽子を両手で押さえながら笑っていた。
「あなたがこんなに可愛らしいなんて、思いもよらなかったわ。」
おかしくてたまらない、という顔で妹を見つめている。
「可愛らしい…ですと?、思いもよらない…ですと?」
条件反射的に反芻してから、その込められた意味にオスカルの目がつり上がった。
つまりは、今まではちっとも可愛いと思っていなかった、ということである。
「アンドレは昔からニコニコして本当に可愛かったけれど、あなたはいっつも気むずかしい顔をしていたもの。可愛いわけがないじゃない?ねえジャン。」
クロティルドは罪のないジャンを味方に引き入れようと、極めつけに優しい声で船尾に立つ漕ぎ手に同意を求めた。
「い…や、クロティルドさま。お小さいときは、どなたさまもみんなお可愛かったですよ。」
うまくかわしたジャンにアンドレは内心賛辞を送った。
使用人の鑑だ。
「見た目が可愛かったかどうかはともかく、わたくしは常に正々堂々、己の義務を果たして参りました。何せ武人でございますからな。可愛いなどという代物は、持っていたところで毒にも薬にもならぬのです。」
オスカルが厳しい口調で切り返した。
良き縁談を求める令嬢ならばいざ知らず、当主として家を守るべく育った身である。
可愛い必要がどこにあるか。
「ほら、そうやって真面目に反論してくるところ。それが堅苦しいのよ。」
確かに、この発言を聞く限り、ジャンのほうがよほど洒落ている。
アンドレはクロティルドとともにクスクスと笑った。
そして感傷的になっていたオスカルの気持ちをすっかり回復させてくれたクロティルドにそっと感謝した。
まったく、このお方は意図せずに自分たちを幸せな心地にしてくださる。
いったいどんな船旅が待ち受けているのだろう。
アンドレは顔を上げ、船の前方に目をやった。
「運河に合流します。」
ジャンが号令のように叫び小船を水路から運河に漕ぎ入れた。
後続の荷物を積んだジュールの舟も同じように続く。
水路に比べれば川幅は倍ほどに広がった。
その分、流れも緩やかになる。
日はまだ東方にあり、運河の蛇行に合わせて差し込む方角が変わる。
ときにオスカルの正面から日が当たって、彼女はまぶしそうに目を細めた。
するとアンドレがさりげなく自身の位置をずらし、オスカルが自分の日影に入るように動く。
運河を行く間、その動作が何度か繰り返された。
「ねえ、今、気づいたのだけど、オスカルが光でアンドレが影のように見えて、実のところは、オスカルがアンドレの影に隠れているのね。」
クロティルドが大発見をしたように甲高い声を出した。
指摘されて、二人は心臓がドキリとはねた。
ひょっとして昨夜の会話を盗み聞いたのか。
アンドレは、「地獄の果てまでおまえの影だ。」と言ったのだ。
オスカルとアンドレは、まさか、という顔で目を見合わせた。
だが、クロティルドはお構いなしに続ける。
「きっと昔からそうだったのね。オスカルって、人前ではえらそうに肩肘這っているけれど、誰もいないところでは、いつもアンドレに影を作ってもらってたんでしょう?」
こちらの反応にお構いなくたたみかけてくる。
「聞き捨てなりませんな。そのような乳母日傘(おんばひがさ※下に注釈)のような言い方。わたくしはこれでも部下を率いる軍人ですぞ。」
「あら、まあ、なんてぴったりな言葉でしょう。乳母の孫が作った日陰というわけね。ちゃんと自覚してたなんて、またまた見直したわ。」
クロティルドはオスカルの抗議の内容には一切耳を傾けず、乳母日傘という言葉にだけ激しく反応して声高く笑った。
オスカルは、脱力して姉との会話をあきらめた。
もとより姉上たちの中で、まともに会話が成立するのはカトリーヌだけだ。
マリー・アンヌもかろうじて意志の疎通がはかれるが、ジョゼフィーヌとは衝突以外したことがないし、クロティルドとオルタンスにいたっては、おそらく生きている世界が違いすぎるのだ。
ジャルジェ家の跡取りとして、姉妹中で最も厳しく育てられた自分に対して何たる言いざまであろうか。
オスカルは姉からあからさまに顔を背けた
その一方でアンドレは思いもかけない指摘に顔を赤くしている。
その様子が、クロティルドには何とも可愛らしく、また愛しくもあった。
旅立ちは寂しいもの。
自分もそうだった。
両親のいるベルサイユから、同じように船に乗ってノルマンディーに向かった。
けれど、一人ではなく夫がいた。
新しい生活、新しい世界への希望もあった。
きっと妹も、あのときの自分と同じはずだ。
というか、同じであってほしかった。
別れゆくものへの感傷は、それはそれとして、これからの船旅は心楽しい物にしてやりたい。
でなければ、同船する自分が楽しくないもの…。
クロティルドは、一応彼女独特のやり方で妹を気遣っているつもりだが、本音のところは自身のためらしい。
したがって彼女なりの善意が相手に届こうが届くまいが、一向気にするつもりはない。
それは受け手側の器量の問題なのだ。
すべるように進む舟の行く手に、ゆったりと流れるセーヌが見えてきた。
「まもなくセーヌに合流です。クロティルドさま。お船はどちらに?」
「合流点から少し下ったところよ。河岸に桟橋がつくってあって、そこに係留しているはずなの。舟から直接乗り移るのは危険だから、一旦河岸に着けてちょうだい。そこからは歩きます。荷物の方も、取りに来るよう指示しますから、同様にね。」
ジャンは、後方のジュールに大声でクロティルドの指示を伝えた。
運河からセーヌに入ると、景色ががらっと変わった。
両岸が運河とき比べものにならぬくらい離れていて、視界が一気に開けた。
大小の船が忙しそうに行き交っている。
前方の大型船のマストにいた見張りがクロティルドの姿を認め、何か叫んだ。
駆け足で船を下り、河岸を走ってこちらに向かってくる水夫たちに、クロティルドが手を振った。
セーヌの水量は豊かで、清濁の全てを抱き込んで堂々と流れている。
ゆっくりと着岸した舟から、三人は静かに降り立った。
※幼児に、乳母をつけたり、強い日に当たらぬように傘を差しかけたりすること。子供が大事に育てられること
BACK NEXT MENU TOP BBS