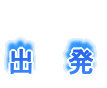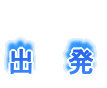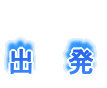クロティルドが、船をパリに向かわせるために出した条件は、ただ一つ。
絶対にオスカルが下船しない、というものだった。
船内軟禁状態に耐えるなら、進路を上流にしてもよい。
だが、たとえ船がパリ市内のどこかに停泊しても、絶対に降りてはいけない。
情報が欲しければ、アンドレ、もしくは水夫を使うこと。
「さあ、お返事は?のめないなら、船はこのままノルマンディーよ。」
広くない船室で、クロティルドはオスカルの正面に立ち、答を迫った。
アンドレは、いつものようにオスカルの斜め後ろに控えている。
たとえ下船できずとも、とりあえずパリに向かいたい。
衛兵隊が寝返ったというその場に、できるかぎり近づきたい。
そのためなら、どんな条件でものむつもりだった。
「承知いたしました。」
「二言はないわね?」
「もちろんでございます。」
クロティルドはオスカルの船室から甲板にあがり、待ち構えていたアラン・ルヴェに、進路変更を告げた。
アラン・ルヴェは黙ってうなずいた。
船の碇が上げられた。
「出航!」
アラン・ルヴェのわれ鐘のような声が響き渡った。
ノルマンディーからあがってきた船は、まだ船首を上流に向けたまま停泊していたから、パリに向かうのならば、方向転換する必要がなく、きわめてスムーズに動き始めた。
だが、たとえ緩やかな大河とはいえ、流れに逆行するわけであるから、オスカルのあせる気持ちに添うようなスピードは望めなかった。
マストの向きを調整し、風をうまく受けた上で、船底では屈強な男たちが必死で櫂を動かしていた。
瀟洒な作りの船室にひとりこもったオスカルは、椅子に座って手を組み神に祈り続けた。
一方アンドレは、甲板に出て、次々とセーヌを下ってくる船からの情報を、収集していた。
船乗り同士は、たとえ違う船でも同志意識が強い。
声が聞こえる距離に近づいたら、船の大小を問わず、パリはどうだ、と問うてみる。
たいがいはすれちがいざまに、知っている限りのことを教えてくれる。
そうやって小刻みではあるが、情報は集まってきた。
衛兵隊の出動場所はテュイルリー宮広場である。
そこに詰めていたランベスク公率いるドイツ人騎兵隊に、飢えた民衆が投石したことから、兵士が発砲、広場は乱闘の巷とかし、血の渦にまきこまれた。
そして、その知らせを受けた出動途中の衛兵隊は、すぐさま広場に急行し、ドイツ人騎兵の援軍たるべきところ、一致団結して寝返り、民衆の側についた。
現在、手にしている情報はそこまでである。
現在も戦闘が続いているのか。
あるいは、すでに停戦をみたのか。
結果はおろか経過すらわからない。
血の渦の中に身を置き、死にものぐるいで戦う部下の姿が脳裏をよぎる。
その先頭に立ち、一歩もひるまず、声をからして指揮をとるアランの大粒の汗までが、目に見えるようだ。
本来なら、自分が立つべき場所。
自分が指揮すべき部下。
それなのに、自分はのうのうと船の流れに身を任せ、こんな船室で、祈るほかに術がない。
ああ、いたたまれない。
すぐにもここから飛び出して、部下とともに銃を取り、戦いたい。
しかし、それは許されないことだった。
おそらくクロティルドの指示であったのであろう。
船は通常の倍ほどの時間をかけて、進んでいた。
そしてパリ中心部に入る手前で、セーヌの左岸に着岸した。
もう少し上ると、シャン・ド・マルスがあり、さらに進むとテュイルリー宮広場である。
間違っても流れ弾や砲弾の被害に絶対に遭わない安全地帯が、アラン・ルヴェの選んだ接岸地点だった。
すでに夕刻である。
船のとも綱が固く結ばれるや、すぐに水夫たちが下船して、市内に散った。
できるかぎり情報を集めてほしい、とのクロティルドの依頼を受けた屈強な水夫たちだ。
おのおの、バルトリ候のお供でパリには何度も来ており、なじみの店や人間がいた。
危険を感じたら、すぐに戻ってくるように、というクロティルドの言葉を、彼らはそろって笑い飛ばした。
難しい理由はいらない。
奥さまのお願いなのだ。
船の男が命がけで働くにこれほど充分な理由はない。
同時にアンドレも船を下りた。
向かう先はベルナール宅である。
おそらくベルナールは不在だろう。
しかし、ロザリーは自宅にいるはずだ。
あの愛妻家が、このような危険なときに、妻を外に出すわけはない。
アンドレは、ロザリーからパリの現状を聞くつもりだった。
船内には、クロティルドとアラン・ルヴェ、そして万一の事態に備えて数人の水夫が残った。
約束通り、オスカルも待機している。
一度、クロティルドが様子をのぞきにオスカルの船室に来たが、飛び出す気配はないと判断したようで、そっと飲み物だけ置いて出て行った。
時計の音が狭い船室でいらだたしげに響く。
長い時間をかけて、オスカルは姉が置いていったグラスを飲み干した。
戦闘現場の様子とともに、まだ銃声の聞こえる町に向かったアンドレのことも案じられて、まんじりともせず過ごした。
やがて日が落ちた頃、あちこちに散らばっていた水夫が次々に帰船した。
賑やかな外の音にオスカルが顔を出すと、クロティルドが立っていた。
「アンドレはまだだけれど、とりあえず報告を聞きます。あなたも甲板に出ていいわよ。」
クロティルドの許可が出て、オスカルは甲板にあがった。
車座になった水夫たちが、次々にクロティルドとアラン・ルヴェに報告を始めた。
パリ市内に運び込まれる物資にはすべて税がかけられる。
入市税である。
その取立所が前夜から焼き討ちにあっていて、まだ煙が消えない。
そう話す水夫は、よほど近くまで言ったのだろう。
顔がすすけていた。
「なんてったってよぉ、市内の54の取立所のうち40カ所が焼かれてるんだぜ。」
厳しい徴税が、市民の怨嗟の的であったことが、この一事でも証明されている。
ましてその税の使い道が、王妃の贅沢三昧の暮らしだと市民が思ったとすれば、彼らの憎悪は否応なくマリー・アントワネット個人に向かうだろう。
オスカルが最も恐れていたことである。
国の財政が立ち行かなくなったのは、何も王妃ひとりの責任ではない。
だが、得てして群集心理は、攻撃対象を絞り込むことで結束をはかる。
「市民軍を作るって話になってるらしいぜ。各地区から800名ずつ。60地区で48,000人だ。すげえ規模だな。」
頭をスカーフで巻いた男が続いて報告する。
「それは机上の空論だろう。そのようなにわか編成ができるものではない。第一武器はどうするのだ?」
オスカルが軍人らしく質問する。
「そうよ。それが肝心かなめなんだ。市内の貴族の屋敷を襲って武器を調達するっていう奴らもいて、市長が仕方なく役所の分を出したらしい。」
「市庁舎に配備されていたものだな。だがあそこの武器はせいぜい小銃で、400丁にも満たないはずだ。それでは到底足りないな。」
またしてもオスカルが的確な判断で質問を繰り出す。
「だんな、詳しいねえ!市庁舎のは小銃360丁だってよ。だんなの言うとおり、全然足りねえってんで、今度は廃兵院に武器を出せって言ってるらしい。」
水夫はオスカルが男だと思い込んでいる。
事態が取り込んでいるので、クロティルドも気づかないのか、あえて訂正しない。
「なるほど。だがあそこはそう簡単には出すまい。」
「ああ、渋ってるらしい。明日、廃兵院に押しかけるって話だった。」
騒然とした空気がこの船上の甲板にまで流れ込んでくるようだ。
ひっきりなしに聞こえていた銃声は日没によって収まってはいるが、時々、暴発するような音が聞こえる。
その闇の中から、アンドレが戻ってきた。
「オスカル、衛兵隊はとりあえず死者は…ない…。」
肩で大きく息をしている。
全速力で駆けてきたのだろう。
息を落ち着かせた後、アンドレはゆっくりと詳細に報告を始めた。
衛兵隊はテュイルリー宮広場に到着するや、市民の前に出て、ドイツ人騎兵隊との銃撃戦を開始した。
王室倉庫などを襲い、すでに武器を手にしていた市民がこれに加勢して、衛兵隊は俄然優位になった。
やがて、市民と衛兵隊の猛攻撃に、ドイツ人騎兵隊は、マルス練兵場に撤退。
衛兵隊は警戒態勢をひいたまま、一夜をあかすことになった。
市民側には多数の負傷者が出ているが、駆けつけたクリスが、ディアンヌとともに治療に当たっている。
衛兵隊で銃弾を浴びたのはフランソワとジャンだった。
幸い命に別条はないが、出血が多いので、ベルナールが二人を自宅に連れ帰り、ロザリーが看病している。
アンドレは、ちょうどその手当の最中にベルナール宅に到着したので、ベルナールにも、フランソワとジャンにも直接会って話が聞けたのだ。
二人はアンドレが突然来たものだから、大層驚いていたが、オスカルも船でそこまで来ていると聞いて、随分と喜んでいた、とアンドレは伝えた。
「本当に、二人の傷は大丈夫なんだな?」
「ああ。あれだけしゃべれたら大丈夫だろう。ちょっと痛々しいが…。」
「そうか…。よかった…。で、アランは?」
突然、アラン・ルヴェが怪訝そうな顔をした。
「ああ、すまない。私の部下のアラン・ド・ソワソンのことだ。」
「ふん、紛らわしい!」
ぶつぶつとアラン・ルヴェがこぼす。
アンドレはクスリと笑った。
「見事な指揮だったらしい。」
「負傷者の数を見ればわかる。死者を出さなかったとは、たいしたものだ。さすがだな。」
アランが直接聞いたら、真っ赤な顔で否定しながら、人目がないところでは涙を流して喜ぶような賞賛だった。
直接聞かせてやりたいな、とアンドレは思った。
が、アンドレでさえ、アランには会えていない。
オスカルがアランと再会できるとは思えなかった。
「ベルナールがしきりにコミューンにほしがっていた。」
「コミューン?」
「ああ。三部会の平民代表を選ぶ選挙人のグループが、選挙後も市役所に陣取って非公式の団体を結成していたらしい。それがこのたび常設委員会になって、選挙人の他に市長や役人も参加した。アランも衛兵隊の代表としてその委員になれということだ。」
「あいつ、断っただろう?」
「ああ。」
「アランは政治向きじゃない。生粋の軍人だ。」
「だが、市民軍には司令官が必要だ。ベルナールは粘り強く説得すると言っていた。」
「政治向きじゃないアランって、こっちのアランと一緒じゃねえか。」
水夫の一人が大声で言って、ドッと笑い声があがった。
「馬鹿野郎!俺は軍人じゃねえぞ!」
アラン・ルヴェが怒鳴り返す。
「こっちは生粋の船乗りだあ!」
またドッと笑い声が起きる。
それを横目に、オスカルはあらためてアンドレに質問する。
「明日はどうなる?ベルナールとアランの読みは?」
先ほどの水夫の報告では、市民は廃兵院に向かうと言っているらしい。
とすれば、衛兵隊もそちらに向かうのか。
廃兵院はセーヌの左岸にある。
つまり、今、オスカルたちが停泊している側である。
だが、廃兵院には武器だけだが、火薬や銃弾のある場所がパリ市内にはある。
もし、市民がそこに目をつければ…。
「コミューンの代表は廃兵院の他にバスティーユ牢獄にも交渉に行くと言っていた。」
アンドレの答えにオスカルは、やはり…、とうなずいた。
やはりそこに目をつけたか。
聞くべき情報を全て手にしたオスカルは、クロティルドと水夫たちに礼を言うと、アンドレとともに船室に戻った。
「危ない目に遭わなかったか?」
扉を閉めるなり、オスカルは聞いた。
「これでも、もと衛兵隊員だ。」
アンドレが笑った。
「一緒に行ければよかったのだが…。」
アンドレの顔が凍り付いた。
「やめてくれ。そのほうがよほど俺には危険な状況だ。」
「わかっている。ばれて船を出されたら元も子もない。ここは姉上との約定を守るしかないのだ。」
そういう問題ではない。
身重の人間が争乱の町をうろつくことの恐ろしさを言っているのだ。
だが、どれくらいわかっているか、はなはだ疑問だったが、とにかく下船はないという約束だけは守ってくれそうで、アンドレは胸をなで下ろした
「明日はパスティーユだな。」
オスカルは、アンドレの肩に頭をのせた。
もしそこを落とせば、市民軍は武器と弾薬の両方を手にする。
そして、対等となった市民軍は、その中核をなすであろう衛兵隊は…。
さらなる戦いに突入するのだ。
アンドレは黙って、力強くオスカルを抱きしめた。
胸の鼓動が重なり、ゆっくりとオスカルの不安と緊張が解けていく。
喜びをともにし、苦しみをわかちあい、近く近く魂を寄せ合い…。
今までも、そしてこれからも、世の中がどう変わろうと、それだけは変わらない。
互いのほほえみも、声も、永遠に互いのものだ。
1789年7月13日の夜、流れるセーヌの上で、船は静かに揺れていた。
※参考資料 「図説フランス革命」 芝生瑞和編 河出書房新社
BACK NEXT MENU TOP BBS