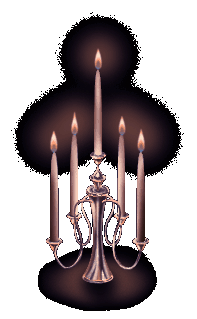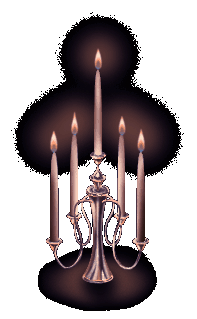
妻が離縁を求める。
子供の勘当を求める。
そんなことが現実に起こるのか。
だが、ついさきほど、将軍は確かに自身の耳で、妻の言葉を聞いた。
初めて聞く妻の怒声。
凛として、張りがあって、自ずと周囲が耳を傾けてしまう、怒りを含んだ妻の声。
初めて…、いや、違う。
初めてではない。
昔、ずっと昔、自分は、あの声を聞いたことがある。
将軍は、娘の部屋からひとり書斎にひきあげ、晩餐にも出ず、じっと座り込んでいた。
大きな両袖机に燭台をひとつ置き、あとは戸外の月の光だけ、という暗闇で、ぼんやりとあの声を聞いた時を思い出していた。
明るい日差しのパリのカフェ。
行き交う人々と、士官仲間たち。
ささいなことから討論となり、自分の手首から鮮血が走った。
そのとき、どこからともなく駆け寄ってきた少女は、たおやかな見かけに似合わぬ大声で、見ず知らずの客たちに命じていた。
「みなさまがた、持っておいでのハンケチやスカーフをすぐにお出し下さいまし!」
そうだ。
凛として、張りがあって、自ずと周囲が耳を傾けてしまう、怒りを含んだ声。
続いて、腰に剣を下げたいかつい士官にも、端的な命令を下していた。
「ブイエさまでいらっしゃいましたね。そのクラバットを貸してくださいな。ジャルジェさまのお顔が青くなってきております。お早く!」
舞踏会での出来事など全く意に介さず、彼女は堂々とブイエにも接していた。
ああ、そうだ。
ブイエが宮殿で言っていた。
奥方が気の毒だ、と。
あの少女は、まだ医師見習の苦学生だったラソンヌを有無を言わせず馬車に引っ張り込み、ジャルジェ家まで送り届けてくれた。
武官の妻にこんなにふさわしい令嬢はいるまい、と両親そろっていたく気に入り、当人同志の意志の確認などまったく棚上げのまま、縁談はとんとん拍子に進んだ。
「どちらも嫌だと言わないのですから、きっと憎からず思い合っているに違いありません。あんな性格の子ですもの。こちらが万端お膳立てしてやらなければ、一生嫁などもらえませんわ。」
先代のジャルジェ夫人はこともなげに言い、一年後には、少女は妻となった。
少女の方も、最後まで嫌だと言わなかった。
明るく快活で、健康で、どんな話題にも興味深げにうなずき、ときには鋭い意見も言っていた妻が、次第に口数少なくなっていったのはいつからだっただろう。
次々に授かる子供がみなそろって女児だった。
もちろん、はじめから焦りがあったわけではない。
健康に生まれたのなら良い、と当主の父も笑っていた。
長女のマリー・アンヌなど、乳飲み子のうちに公爵家との縁談をまとめて、先々楽しみだと話していた。
次女のクロティルドのときも、健康であれば、まだまだ授かると、自分も笑っていた。
三人目が娘だったとき、かすかな圧力を感じた。
父からか、母からか、あるいは一族からか。
だが二人はまだ若い。
いつかは男子が授かるだろう。
にぎやかになった屋敷で、将軍は男子の誕生を信じて疑わなかった。
四女のカトリーヌが生まれるまで元気だった父は、跡継ぎの誕生を心待ちにしたまま、亡くなった。
そして母も、五人目が生まれる直前に父のあとを追うように旅だった。
今度こそ男の子よね、と死の床で笑っていた。
だが一族の期待を一身に集めての五度目の出産も女児であった。
爵位を継いだ自分とともに、晴れて伯爵夫人となっていた妻は、五人の娘達を手元に置き、乳母はやとったものの、出来る限りマロンの助けを借りて、自身の手で教育を施し始めた。
明るく快活だった性格は、穏やかで従順になり、将軍はそれを好もしいものと受け止め、何の疑問も抱かなかった。
少女が妻となり、母となったのだ。
性格の変遷は当然だと思っていた。
おそらく最後の出産だと覚悟し、一縷の望みを託した六度目の出産でまたもや女児が生まれたとき、あまりの落胆と衝撃から、男子として育てる、と妻に告げた。
彼女は大きく瞳を見開き、ただ黙って赤子を抱きしめた。
もとより妻の意見など聞くつもりはなかった。
いや、妻に意見があるなどと、思ったこともなかった。
たった今まで…。
何十年ぶりで聞く妻の意見が、離縁だとは…。
蝋燭が短くなってきていた。
反対に月の光は増していた。
勢いを失っていく蝋燭に自分が重なり、決して裏側を見せようとしない月に妻が重なる。
月は遠くて届かないけれど、妻はすぐ側にいたのだ。
自分が心の裏側に立ち、察してやっていれば…。
なぜ、六女を男として育ててしまったのだろう。
なぜ、妻の気持ちに気づいてやれなかったのだろう。
オスカルとアンドレのことは、気づいていた。
結婚しているとは思わなかったが、目の治療でアンドレをパリにやったのは、オスカルの気持ちを知っていたからだ。
末娘がアンドレを必要としていることが、ありありと見えたから、そのの失明を見過ごすわけにはいかなかったのだ。
武人として生きるオスカルのそばにアンドレを置いておくことがせめてもの親心だった。
だが、ジェローデル少佐との結婚を断り、武人として生きると言い切った娘が、すでに女としての人生を捨てたと思っていた娘が、母になるという。
「オスカルを解放してやらなければなりません。」
再び妻の言葉が響く。
すべてのはじまりは自分の決断だった。
終止符を自分以外の人間に打たせるのは本意ではない。
将軍はゆっくりと立ち上がると、燭台の火を吹き消した。
そして窓辺に立ち、月を見上げた。
明るい少女の顔がそこに見えた。
やがて月に背を向けると、書斎を出て、将軍は大広間に向かった。
妻と娘たちが、遅い晩餐についているはずだった。
彼は長い廊下をしっかりとした足取りで歩いていった。
BACK NEXT MENU HOME BBS
月と蝋燭