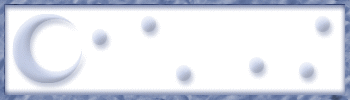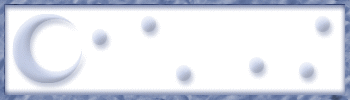-7-
アンリ時計店では光を失ったジョベールに代わって、息子のヤンが取り仕切っている。
修理技術の腕は父親に及ばないので、もっぱら修理などの仕事は父の弟子に任せているらしいが、人当たりがよいため接客には向いている。
なにごとも適材適所なのだろう。
その愛想の良いヤンがジャルジェ家には一層丁重ににこやかに応対してくれるのは、一重にオスカルとオルタンスの好意に感謝しているからだ。
おかげで、使用人という立場のアンドレが行っても恐縮するほど丁重に迎えてくれた。
さっそく懐中時計を箱から出した。
「なおりますか?」
「年代物ですね」
古ぼけた安物だと思うが、そういう風に言われれば悪い気はしない。
「2週間ほどみてください。きっと修理してお届けにあがりますよ」
太鼓判を押してくれた。
よかった。
アンドレにとっては親の形見だ。
動かぬまま保存するよりは、実際に使えるほうがずっといい。
ましておばあちゃんの胸元にいつもぶらさがっているならば、なおのこと正確に時を刻んでいてほしい。
そうすることで、きっと祖母は娘とともにいると感じられるに違いない。
アンドレは気分良く時計商を後にした。
夕方とはいえ、まだ日はある。
まぶしげに通りの向こうに目をやると、驚いたことに点いたばかりの外灯の下でフェルゼン伯爵が立っていた。
アンドレに気づいて、やあ、と手を挙げている。
急いで駆け寄った。
「伯爵!もういらしてたんですか?」
アンドレは、当然自分が待つつもりだった。
だからフェルゼンと6時の約束のところ、5時には時計店に来たのだ。
そしてヤンとは10分ほど会話しただけだ。
伯爵はいつから待っていたのだろう。
「思ったより近かったのだよ。というか、知らないところだからと用心して早めに出たら、辻馬車の御者がこのあたりには詳しくて、すぐに着いてしまったのだ」
さりげない気遣いが伝わってくる。
「すみませんでした」
並んで歩き出すと、上品な香水のにおいが漂ってきた。
身だしなみに隙のない人だと感心する。
「よく出てこられたな、オスカルは?」
「奥さまと一緒に姉上さまのところに行っています」
「なるほど。それは好都合だった」
笑い顔もさわやかだ。
「この角を曲がったところです」
重厚な木製の扉の前で立ち止まった。
「変わった名前の店だな。来たばかりなのに帰らねばならないような気がしてくる」
フェルゼンが看板を見て首をかしげた。
ちょうど店のものが、入り口の灯りを入れに出てきた。
「ちょっと早いがかまわないか?」
アンドレが声をかけると、男はうなずいて店内に案内してくれた。
時計店に来る前に先にこちらに寄って予約を入れておいたのだが、来店は6時頃と伝えてあった。
まだ5時を過ぎたばかりだ。
「奥の席は今夜はこちらさまの専用にしてますから、どうぞゆっくりお使い下さい」
まだ店名にぶつぶつ言っているフェルゼンを無視して、店員は入り口付近のテーブルを器用に除けカウンターの横の通路をさらに進んだ。
そのつきあたりがついたてでで仕切られ半個室になっていた。
大きめのテーブルに椅子が4脚。
入り口からは完全に死角になっている。
小さい声ならば他の席に聞こえる心配もなさそうだ。
確認済みだったとはいえ、アンドレはホッとした。
フェルゼン伯爵はある意味有名人だ。
顔を知っている者が周りにいないとは限らない。
それでなくともゴシップビラには風刺画が満載で、フェルゼンと王妃の密会シーンがまるで見てきたかのように書き立てられているのだ。
恨みに思う市民は多い。
まかり間違えば、オスカルの馬車が襲われた二の舞になる可能性も否定できない。
本当ならパリで会うべきではなかったのかもしれない。
だが、ベルサイユでは伯爵はパリ以上に有名なのだ。
貴族ならビラではなく実物のフェルゼンを知っている者がパリの比ではない。
誰の目にとまって、オスカルの耳に入るとも限らないわけで、ならばまだパリの方が人混みに紛れ込める分マシというのがアンドレの判断だった。
そのため店は、大衆向けでもなければ貴族向けでもない中間的なレベルのものを選び、さらに通りから一本入ったところにしておいたのだ。
この店は以前フランソワが、本命の女をくどくときに連れてくる店だと教えてくれたものだ。
はじめて来たが、確かに感じの良い店で、飲み屋というよりは食堂のような構えだった。
だが酒の品揃えは豊富だった。
フェルゼンはメニューに釘付けだ。
あまり強いようには思わないが好きなのだろう。
たくさん飲めない分、厳選したいという姿勢だ。
「やはり最初はシャンパンだな」
フェルゼンの言葉でアンドレが給仕をよんで注文した。
「シャンパーニュ伯爵を知っているか?」
ふいにフェルゼンが聞いてきた。
「いつのですか?」
「もちろん吟遊詩人のチボー4世だよ」
「十字軍に行った?」
「そう、その人」
「あまり歴史は得意ではないんですが…」
オスカルなら1時間は語ってくれそうだが、自分はもっぱら聞き役だから、と心の中で言い訳をする。
「わたしも深くは知らない。だが、フランス王妃に恋い焦がれて国王に疎まれて、十字軍に行った人だと聞いている」
アンドレは初耳だった。
「その人が遠征からの帰途にキプロスから持ち帰っブドウの樹がシャンパンの始まりだ、これも又聞きだかがね」
「そうだったんですか」
「まるでわたしのようだろう?」
「…」
「国王陛下にあからさまに疎まれたことはないがね」
自嘲気味に笑っている。
それでもフェルゼンはアメリカ独立戦争に行った。
醜聞から王妃を守る為だった。
フランス国王ルイ8世の王妃ブランシュ・ド・カスティーユに熱愛を捧げたたシャンパーニュ伯爵。
フランス国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットに魅了されたフェルゼン伯爵。
かたや十字軍へ。
かたや独立戦争へ。
「古い話だが、結局昔も今も男というものはどうしようもない、ということだ」
給仕がグラスを二つ持って来た。
シャンパンの泡が涼やかにはじけて美しい。
「きみならわかるだろう?」
フェルゼンがアンドレのグラスにコンと自分のものを合わせてきた。
アンドレは黙ってうなずいた。
「シャンパーニュ伯爵は実にたくさんの詩を残している。そのうちのひとつが、‘もう恋などするまい ’というのだ」
白い透明な液体がフェルゼンの口元に吸い込まれた。
「切ない詩ですね。題名だけでつらくなる」
「だろう?だが、惹かれるんだ」
「どうしようもなく?」
「ああそうだ。人は笑うのに」
つらい恋の連鎖だったのだ。
アンドレは寂しく笑うフェルゼンを見て思った。
自分はオスカルに恋い焦がれた。
オスカルはフェルゼンに恋い焦がれた。
フェルゼンは王妃に恋い焦がれた。
そして王妃もフェルゼンに恋い焦がれた。
だが国王の妃だった。
思いは通じ合っても成就しない。
きっと国王も妃を愛していた。
そしてこちらは結婚しているのにも関わらず報われない。
男三人と女二人。
そろいもそろってつらい恋ばかりだったのだ。
いや、自分以外は全員貴族だ。
自分だけが平民であることを思えば、この連鎖の中に入る資格すらなかったのだろう。
だが、実際にはどうか。
オスカルはアンドレを愛していると言ってくれた。
そして妻となってくれた。
一番幸せなのはおれだったのだ、とアンドレはあらためて知った。
あれほどうらやましく思ったフェルゼンに今は深い共感と同情すら感じている。
「笑いたい人には笑わせておけばいいんです」
アンドレがぽつりと漏らした言葉にフェルゼンは少し眉を上げた。
「‘もう恋などするまい ’…そう思えるのは本当に恋したことがある者だけです。笑う奴らにはそんな経験がないんでしょう」
「つらくても、しないよりはいいと?」
「そう思いませんか?あの方に出会わなければ良かったと思ったことがありますか?」
フェルゼンは少し考え、それから首を横に振った。
「一度もない」
「ならば出会って良かったのですよ」
「なるほど。出会って、恋をして…」
「良かったのです」
「きみもそう思っているか?」
アンドレは即座に首を縦に振った。
「まったく迷いはないんだな」
大したものだとフェルゼンは笑った。
ようやく食事が運ばれてきた。
チキンを焼いた香ばしい匂いが漂う。
店内が賑やかになっていることに気づいた。
ついたてのおかげで見えないが、席が埋まりはじめたようだ。
二人は目配せをして声のトーンを落とした。
フェルゼンがオスカルと初めて会った時の話を始めた。
それは初めて王妃に会った日でもあった。
「若造と言われたのだ」
「オスカルに?」
「ああ、同い年だとあとで知ったが、あいつも充分な若造に見えたのでムッとした」
クスクスとアンドレは笑った。
「そのうえ名を名乗れと来た」
「オスカルらしい」
「だから、そっちから名乗るのが礼儀だと言ってやったんだ」
「ごもっともです」
そして近衛士官だと知り、一目で心惹かれた女性が王太子妃だと知った。
「正式に謁見を申し込めと言われた」
致し方あるまい。
あの頃のアントワネットは舞踏会に夢中だった。
舞踏会だけではない。
楽しいことに夢中だった。
そしてこのパリが大好きだった。
今もそうだろうか。
「ここですよ~」
ついたての向こうで大きな声が聞こえた。
聞いたことのある声だとアンドレは思った。
少しいやな予感がした。
「本当に来てくれたんですね、ありがとうございます」
間違いない。
フランソワだ。
アンドレはあからさまに顔をしかめた。
フランソワに教えられた店に来るということは、こういう可能性もあったのだ。
金のないフランソワが、しかも本命と来るところだと言っていた彼が、今夜に限ってやってくるとは思わなかった。
「伯爵、すみません。どうやら知った奴が来たみたいです。そいつらが帰るまでここから動けません」
おやおやと言いながら、全然困った素振りも見せず、フェルゼンはチキンを食べている。
「もとよりそんなに慌てて帰る必要は無いのだから、一向に構わないさ」
フェルゼンは気にも留めていない。
そう言われればそうだ。
こちらが席を立たない限り、顔を会わせることはないのだから、ゆっくりと酒と会話を楽しめばいいのだ。
それにしても一体誰と来たのだろう。
まさか本命を連れてきたか、と思いつつ、アンドレもチキンを食べ始めた。
酒宴1 BACK NEXT HOME BBS MENU