オスカルとアンドレが出会ったのは、二人が7才と8才の時だった。
いきなり剣を手渡されたアンドレは、そのまま首根っこをつかまれ、泣きながらオスカルの相手をさせられた。
出会いがこの形である以上、二人の立ち位置は、いつもオスカルが主導権を握り、アンドレがその後ろについていく、または引きずられる、というものにならざるを得なかった。
まして、オスカルが貴族で主人、アンドレが平民で使用人となれば、この関係は完全に固定されて、変動しようのないものといえた。
だが、それはあくまで傍目から見た場合であり、実はアンドレは結構反撃していた。
まず、主人であるオスカルを呼び捨てにしているし、敬語も使わなかった。
剣の相手をするときも、決して手加減したりはしない。
だいたい腕前からしてアンドレが手加減して欲しいくらいなのだ。
そしておべんちゃらも言わない。
二人だけでいるときは完全に対等に会話していた。
それは、実はオスカルの希望だった。
ばあやがアンドレに「お嬢さまだよ」と紹介したわずか5分後に、オスカルは言い放ったのだ。
「今後ぼくのことをお嬢さまなどと呼んだら、剣でズタズタにしてやるから覚悟しておけ」
命が惜しいアンドレは、「じゃあ、なんと呼べばいいの?」とおずおずと、お伺いをたてた。
「決まっているだろ、ぼくの名前はオスカルだ」
以来、ズタズタにされたくないアンドレは言われたとおりオスカルと呼んできた。
もちろん祖母にはこっぴどく叱られた。
「お嬢さまとお呼び!」
時には耳をひねりあげられた。
それで、オスカルに祖母を説得してもらうよう、頼み込んだ。
「オスカルがおばあちゃんに言ってくれなきゃ、ぼくはいつかおばあちゃんに殺されちゃうよ。結局、お嬢さまと呼んだらオスカルにズタズタにされて、オスカルと呼んだらおばあちゃんのヤキが待ってるんだ…。そんなの、あんまりだ」
悲壮感が漂っていたのだろう。
オスカルは直ちにばあやへ厳命してくれた。
「アンドレにぼくのことをお嬢さまと呼ばせるな。ぼくはアンドレがお嬢さまと呼んだらアンドレをズタズタにすると言ってあるんだからね。ばあやもアンドレのズタズタは見たくないだろう?」
以後、少なくともばあやはオスカルの前では呼び名のことでアンドレを叱責することはなくなった。
オスカルがいないときには、それでもしつこく注意し、「せめてオスカルさまとお呼び」と言われたが、それはお小言であってアンドレにとっても許容範囲だった。
アンドレ自身、最初はオスカルさまと呼ぼうとしたのだが、「さま付けで呼ぶと本気で剣をあわせられないだろ」と言われ、こちらも禁止されたのだ。
遠慮のない「対等な主従」という不思議な関係は、厳格に見えて結構寛容なジャルジェ将軍に黙認されることで、ジャルジェ家では案外早期に定着した。
したがって、二人の間では主従としてはまずないことだが、喧嘩というものが存在した。
非常にささいなことから、結構大きなことまで、原因は様々だった。
たとえば、である。
基本的に剣が大好きなオスカルは、父の指導もあり、帯剣貴族になるため、義務として剣の練習をする上に、趣味でも剣の手合わせをしたがった。
つまり、剣を使って遊ぼう、となるのだ。
一方、アンドレは使用人であるから、薪拾いやろうそく磨き、馬の世話など諸々の仕事を持っている。
その中にオスカルの剣の相手、という仕事も入っているわけである。
だから、やっと息抜きできる遊びの時間に剣の相手をさせられるなら、それは遊びではなく仕事になってしまうのだ。
もちろん、遊び相手、というのも仕事の一つだと言われれば、従うしかないのだが。
それでも嫌な物は嫌なので、剣で遊ぼうと誘われると、アンドレは露骨に嫌な顔をしたし、他の仕事を口実に逃げ出しもした。
それに対しオスカルが激怒して喧嘩が始まるのだ。
ささいなことではあるが、これは二人が子ども時代のけんかの原因の大半を占めていた。
大きな喧嘩は、実は回数はそれほどない。
二人の価値観はよく似ていたし、物事の好悪も共通することが多かった。
それに屋敷内で同世代が二人だけだったため、なんでも話せるのはお互いだけだった。
アンドレの一歳年長になるオスカルの姉のジョゼフィーヌは、このころからすでにオスカルとは犬猿の仲で、一緒に遊ぶことはなかった。
オスカルは、アンドレだけを同世代の同性、当然だが男同士の友達だと認識していた。
その親友であるアンドレとは、歳を重ねるほどに共感することが増え、もはや自分の考えとアンドレの考えは同一であるとすら感じるほど近しいものとなっていた。
軽口もたたくし冗談も言う。
無理も言えるし、困らせることにも抵抗がなかった。
アンドレは、時にぶつくさ言いながらも、大抵の要望は通してくれた。
王妃から謹慎処分を受けた時も、謹慎せずにアラスへ旅行するという大胆な行動に、顔をしかめつつ同行してくれた。
黒い騎士に変装しろと言った時も、抵抗はしたが、意外な才能で盗人になってくれた。
近衛隊を辞めて衛兵隊に異動すると決めた時も、面と向かっては何も言わず、父の命令に従って軍隊に入ってくれた。
アンドレはいつだってオスカルが真剣に希望することなら、なんでも受け入れてくれてきたのだ。
ところが…である。
最近、その雲行きが怪しくなっている。
転換点はあのときだ。
そう、間違いない。
1788年12月25日。
オスカル33歳の誕生日。
というよりも、オスカルとアンドレの結婚記念日として二人の記憶に刻まれた、忘れようもない日である。
幼なじみで親友で主従でもあった二人が、なんと夫婦になったのである。
関係性に変化が現れるのはむしろ当然なのたが、オスカルにとって、アンドレとの仲は変わらないからこそ信頼できるものだったので、なかなかなじむことができないのである。
アンドレの名誉のために断言するが、彼が突然偉そうになったということではない。
アンドレは、いつでも、どんな場合でも、ひかえめである。
だが、少し強めに出るようになった気がするのだ。
もしかしたら、それはアンドレの変化ではなく、受け止めるオスカルの方の変化なのかもしれないのだが、オスカルには、結婚というかたちをとった自分をまだ客観視できていないため、そういう角度から見ることはできなかった。
「おまえ、変わったな…」
司令官室で書類の決裁をしていたオスカルは、驚くほどテキパキと指令書の下書きを仕上げていくアンドレにつぶやいた。
「え…?」
集中していたアンドレは驚いて顔を上げ、ただ一つの瞳をオスカルに向けた。
「変わったな、と言ったんだ」
「おれが…?」
「おまえ以外に誰がいる?」
「どこが?」
それがわからないからイライラするんじゃないか。
目つきが鋭くなるのを隠す為、オスカルは黙って下を向いた。
‘三部会開会式における近衛隊と衛兵隊の任務分担についての提言’
長々しいタイトルの書類に、署名をする。
「よくわからん」
書類がわからないのか、アンドレがわからないのか、それもわからない。
「言ってるおまえがわからないんじゃ、おれにはわかりようがないな」
アンドレは優しく微笑む。
ちょっとあきれた感じだ。
「自分では気づかないのか?」
トントンと書類をたてて端をそろえながら詰問する。
「まったく…」
「鈍感な奴だな」
「これは失礼致しました」
わざとらしくアンドレはペコリと頭を下げた。
嫌いなデスクワークにイライラしているんだな、と思われていることが手に取るようにわかって、オスカルは一層腹立たしい。
いきなり書類を持って立ち上がった。
「近衛隊に届けてくる」
「自分で行くのか?」
「おまえも忙しそうだ。これくらいわたしにでもできる」
誰もできないとは思っていないが、署名ばかり30回もすればいい加減嫌になって気張らしがしたいのだろうと思ったアンドレは、あえて止めなかった。
オスカルは仏頂面のまま司令官室を出ていった。
※こちらはは第一部の「親子」と「助言」の間の挿話です。
扉 目次 親子 助言 掲示板 犬も食わない2
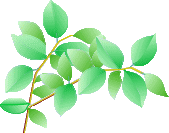

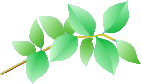

![]()