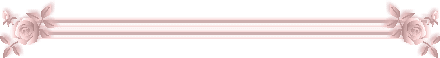
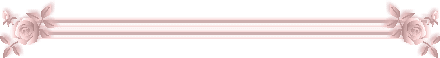
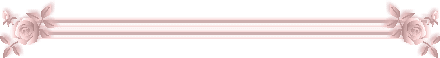
「結局の所、母上は何を持って帰られたのだ?」
「え…?聞いてないのか?」
「教えてくださらなかったからな」
「聞いたのに?」
「いや、聞かなかった」
「知りたいなら聞けば良かったじゃないか?聞けば教えてくださっただろうに」
オスカルは黙り込んだ。
アンドレの言うとおりだ。
聞けばすむことだった。
だが母があまりに大事そうに胸に抱えていたのでためらってしまった。
「おまえは知っているのか?」
「ああ、もちろん」
当然だ。
ばあやの持ち物は一応すべてアンドレのものとなっているわけだから、ジャルジェ夫人といえども勝手には持って行くまい。
一言アンドレにことわりを入れるのが筋というものだ。
「ティーカップだよ」
「?」
「奥さまが持って行かれたもの」
「どんな?」
「見たことなかったか?薄桃色の小花模様をあしらった一対ものだ」
「それはばあやが大事にしていたものなのか?」
「ああ、とても」
ジャルジェ家に奉公に来て初めてのお給金で買ったものだと言っていた。
だから決して高価なものではない。
だが、夫亡き後、一人娘を産んだばかりのマロンがなんとか乳母という職を得て、自分で稼いだお金だった。
ここで誠心誠意働きさえすれば、娘と二人飢え死にすることはないのだ。
生きていける。
その喜びを生涯忘れまいと、記念になるものを買った。
それがティーカップだった。
「これはね、ばあやがうちのお屋敷で生きていた証なのですよ。屋敷に来てすぐに買ったものですからね。お屋敷でずっとばあやとともにあったものなのです」
夫人はそう言って、カップのセットを丁寧に箱に入れて持って帰ったのだ。
「わたしはそんな話は知らないぞ」
「おばあちゃんの昔語りを聞く暇は、おまえにはなかったからな」
なぜだかとても不愉快だった。
ばあやは誰よりもオスカルをかわいがっていたはずだ。
孫のアンドレよりも優先してくれて、アンドレに悪いなと思っていたくらいだった。
それなのに、こうして亡くなってみれば、姉たちとばあやの絆は深くて、知らないことばかりだ。
クロティルドのハンカチ、オルタンスのお針箱、、カトリーヌのロザリオ、マリー・アンヌの眼鏡、そしてジョゼフィーヌの羽根ペン。
姉たちからの返書を読んで、いったいなんなんだ、としばし呆然とした。
だが、母が持ち帰ったティーカップの話を聞くにいたって、ばあやの人生が、当たり前だが一人の人格を持ち、たくさんの人とかかわってきたものだということがわかった。
そんな当然のことに思い至らなかった。
なんと自己中心的に思い上がっていたのだろう。
くやしいが、かつてジョゼフィーヌがばあやへの手紙に書き記したとおり、オスカルは意識しないまま人を見下しているところがあるのだ。
オスカルは自分を恥じた。
「かなり落ち込むな…」
「どうして?」
「どうしてって、自分だけがばあやにとって特別だと思っていたんだぞ」
「その通りじゃないか」
「馬鹿を言え!それは思い上がりだ」
「おばあちゃんにとっておまえが特別だったのは、誰もが認めるところだろう」
「違う!ばあやは誰とも等しく深い絆を持っていたのだ。姉上たちとも、母上とも、そしてもちろんおまえとも…。それが、それこそがばあやの人生だ」
「それはそうだ。それでも、オスカル、おまえは特別だったんだ。それをおまえがわかってくれなかったら、おばあちゃんがかわいそうだ」
「アンドレ…」
「おれは、子どもの頃、おまえにヤキモチを焼いていた。おばあちゃんがあんまりおまえばっかり大切にするから…。笑うな、子どもの頃の話だ」
「おまえに焼いてもらえるとは、果報者だな、わたしは…」
「そうだろう、何せ実の孫だからな」
アンドレの言葉は真実味があった。
オスカルを慰めるための方便とは思えなかった。
それでとても気持ちが楽になった。
やはりばあやはオスカルを最も大切にしていたのだ。
そう信じることができた。
だがアンドレはそれで良かったのだろうか?
実の孫なのに…
「ひとつ教えてくれ」
「なんだ?」
「おまえはどうしてわたしに焼くのをやめたんだ?」
「簡単なことさ。おばあちゃんと同志になったからだよ」
「?」
「おれにとってもおまえが特別な存在になったから…」
アンドレはそう言うとオスカルの頬に唇を寄せた。
熱っぽくて弾力のある唇。
これこそばあやの形見だ。
姉上たちには悪いがわたしがもらった形見はやはり特別だ。
オスカルはその形見に包まれ、そして形見を包んだ。
オキザリス 姉妹Ⅰ 掲示板