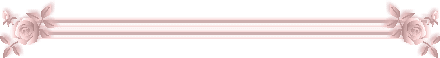
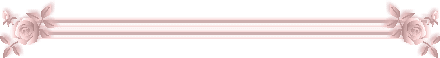
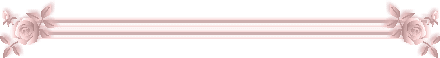
「なんのご用だ?」
アンドレに向かって問いかけたつもりだったが、返事は直接ジャルジェ夫人から返ってきた。
夫人がすでに廊下をこちらに向かって歩いてきていたためである。
その背後に、夫人への挨拶を終えた双子がアゼルマに連れられて外へ出ていくのが見えた。
「ばあやの形見をもらいに来たのですよ」
しっとりとしたブルーのドレスを身につけた夫人は、アンドレとオスカルの脇を抜けるようにしてばあやの部屋に入っていった。
あわてて2人も後に続く。
「ばあやが亡くなってそろそろ2カ月になろうというのに、形見分けが届かないとイングランドの娘たちから手紙が来ました」
「形見分け?」
「そうですよ。皆、それぞれにばあやとの思い出があるのです。なにかしら
「そんなものですか?」
「そんなものです。これがジョゼフィーヌからの手紙です。あなた宛だから持ってきました」
突然母から渡された封書にオスカルの目はキョトンとしたままである。
「ちゃんと読んで、お返事を書いておあげなさいね」
念押しをされて仕方なく封を切る。
が、天敵からの手紙とあって、果たし状のような気配を感じてしまい、すぐには目を通さず、封筒と便箋を握りしめて、窓辺の椅子に腰掛けた。
そんな母娘のやり取りを聞いて、アンドレは自分の至らなさを痛感した。
オスカルにそのような配慮ができるわけはないのだから、これは自分がしなければならないことだった。
それぞれの人柄にふさわしい遺品を選び、生前の祖母への厚情に対する感謝の言葉を添えて、それぞれの元に送り届けるべきであった。
まったくもって申し訳ないことだった。
いつまでも遺品整理をせず先延ばししていたことは慚愧に耐えない。
だが、ほんの少し言い訳させてもらえるなら、祖母の形見をお嬢さまがたのもとに届けるのは、出過ぎたことではないかと思ったのだ。
使用人の遺品など失礼な話ではないかと…。
だから躊躇した。
そしてもしお届けしないのであれば、あえて急いで整理する必要はない。
そのまま、まるで祖母が生きているかのように部屋をおいておくことは、オスカルの希望でもあったのだから。
だが、ジャルジェ家の令嬢たちはそろってアンドレの祖母を懐かしく思い出してくれるという。
「奥さま、申し訳ございませんでした。わたくしの落ち度でございます」
アンドレは心から丁寧に詫びた。
「すぐに皆さまにお届けするものを選びます」
「そうね、アンドレ。ぜひ、そうしてちょうだい」
夫人はにっこりと微笑んだ。
「ただし、わたくしの分は自分で探しますからね」
そういうと夫人は先ほどまでオスカルが触っていたチェストに近づいた。
「このチェストはこちらで新しく買ったのですか?」
「いえ、これはバルトリ侯爵の叔父上のものかと…。家具は一式お譲り下さいましたので、祖母がこの部屋に入りましたときにそのまま使わせて頂きました」
「そうですか。とてもばあやの好みだわ。こういうところには、きっと一番大切なものを入れていたでしょうね」
何気ない言葉に、夫人と乳母との長いつきあいがうかがえた。
アンドレは深い感銘をあえて言葉に出すことはせず、自分も形見の品探しに専念するため、壁際に置かれた飾り戸棚の扉を開けた。
一方、姉からの手紙を読み始めたオスカルのまなじりは、時と共につり上がり、ピクピクと痙攣するほどとなっていた。
先ほどの、子ども時代の手紙そのままの、見事に上から目線のものだった。
結局のところ、四半世紀を経ても、この姉妹の関係は何一つ変わっていないようだ。
オスカルの拳は怒りで震えていた。
わが妹 オスカル・フランソワへ
ごきげんいかが?
ぱあやの遺品を独り占めして、どういうおつもり?
ジャルジェ家の人間があなた一人とでもお考えかしら。
少しでも常識というか、人の心があるのなら、ばあやが亡くなってからすでに二ヶ月も過ぎようという今、ばあやのものが何一つ届かないというのはあり得ないことです。
わたくしの手紙は読まないあなたのこと。
お母さまからお届け頂くのが最善の方法でしょう。
一日も早くこちらへの船便にばあやの形見を乗せなさい。
ジャルジェ家の五女、あなたの姉、ジョゼフィーヌより
追伸 このわたくしの意見にはマリー・アンヌお姉さまも全面的に賛成してくださっていることを付け加えておきます。
「もう読み終わったのですか?」
手紙を握りつぶさんばかりのオスカルを見て、夫人が声をかけてきた。
「ごくごく短いものですから…」
こわばった顔でオスカルが答える。
「わたくしには随分長い手紙をくれたのですけれどね…。とても心にしみるものでしたよ」
地方に嫁したクロティルドやオルタンスと違い、ベルサイユの貴族に嫁いだジョゼフィーヌは、母との交流も密だった分、今になってフランスとイングランドに離ればなれになったことが堪えているのだろう。
気丈なジョゼフィーヌがごくまれに見せる弱気な姿を思い、アンドレは胸が詰まった。
「心にしみるどころか、これはもはや決闘の申し込みでございますぞ!」
突然オスカルが叫んだ。
「え?」
アンドレが反射的に聞き返した。
「どういうことだ?」
オスカルは手紙をアンドレに向かって放り投げた。
「おいおい…。なんてことをするんだ」
アンドレはあわてて両手で手紙を受け止めた。
「読んでみろ!」
言われるまでもなく、アンドレは手紙に目を通した。
そして絶句した。
あまりに正論でぐうの音も出ない。
「おっしゃるとおりだ」
「おまえまでそんなことを言うのか?!」
矛先がアンドレに向き始めた。
「ありがたいことだよ。おばあちゃんのものなんかを手元に置きたいと思ってくださってるんだ」
感受性豊かなアンドレの目はすでに潤み始めている。
「当然ですよ、アンドレ。ばあやはね、娘たちみんなにとってのばあやだったのですから…」
「奥さま…」
アンドレの頬を涙が一筋伝った。
「いいかげんにしていただきたい!」
オスカルがすごい勢いで椅子から立ち上がった。
はずみで椅子が後ろに倒れ大きな音を立てた。
「まあまあ、オスカル。何をそんなに怒っているのです?」
「ジョゼフィーヌ姉上はわたしをまるで常識のない人間のように言っているのですよ!」
「だってその通りじゃありませんか」
「母上…!」
「オスカル、もしもばあやがここではなく、ベルサイユで亡くなっていたとしたら、そしてあなたの元に何一つ形見が届かなかったとしたら、あなたはどう思いますか?」
「しかし…、ばあやの思い出は、物ではない。心です。わたしは形見などなくともばあやのすべてを覚えている。決して忘れたりはしない」
「オスカル、あなたはそうでしょう。あなたのもとには、アンドレも、ミカエルもノエルもいます。これほどばあやにつながる絆はありません。」
オスカルは言葉を失った。
「わかりますね…?」
アンドレがオスカルのそばに来て倒れた椅子を起こした。
背中に大きな掌が添えられた。
それはアンドレの手であると同時にばあやの手でもあった。
開け放たれた窓から風が吹き込んできた。
庭で遊ぶ子どもたちの声が流れてくる。
それはばあやの声でもあった。
ばあやの孫。
ばあやのひ孫たち。
こうしていつもばあやを感じていたのだ。
「ジョゼフィーヌがわたくしにくれた手紙には…」
夫人が静かに語り始めた。
「ばあやの血をミカエルやノエルが継いでくれて本当に良かった。まして二人を産んだのがオスカルだということがとても嬉しい。オスカルは母となって、正真正銘の女になりましたね…と。そんなジョゼフィーヌがあなたに決闘を申し込んだりするでしょうか…」
オスカルの背中に添えられていたアンドレの手が肩にまわり、それから髪を撫でた。
暖かい手だった。
「あの子はね、オスカル、あの子もあなたと一緒、ばあやが大好きだったのですよ。いつもばあやに手紙を書いていたわ。ばあやも忙しい中、お返事を書いていました。その手紙をジョゼフィーヌはずっと取っていたのだけれど、亡命のときに持ち出すことができなかったのですよ。ばあやからの大切な大切な形見だったのですけれどね…」
夫人がまっすぐにオスカルの目を見た。
厳しく優しい、慈しみにあふれた母の瞳に写る己の姿を恥じ、オスカルは眼をとじた。
完敗だった。
「オスカル、一緒におばあちゃんの形見を探そう。そしてジョゼフィーヌさまに送るんだ」
アンドレの言葉にオスカルはコクリとうなずいた。
そして、チェストの引き出しを開けると、手紙の束を取り出した。
「ばあやが取っていた姉上からの手紙です。ばあやも大切に取っていました」
夫人はその束を受け取り、満足そうに微笑んだ。
オキザリス 姉妹Ⅰ 掲示板